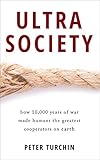今回紹介するのは、 The Atlantic に掲載された、ローレン・カッシーニ・デイヴィス( Larwen Cassani Davis)という Editorial Fellow(編集委員?)による、哲学者・心理学者のジョシュア・グリーン(Joshua Greene)へのインタビュー。
グリーンの著書 Moral Tribes は邦訳もされている。道徳に関する心理や思考のメカニズムを解説するという事実についての既述的なパートと、心理や思考に関する事実を踏まえたうえで功利主義を擁護し他の種類の理論を批判する規範論的なパートがうまく組み合わされているのが魅力的な本である。インタビューでは規範論の方にはあまり触れられていないが。
「感情と道徳性は混ざっているのか?:正と不正の判断に感情がどのように影響するかについて、哲学者が説明する」
日常生活は道徳判断で溢れている。その一部は自動的であり、道徳判断として記録もされない…苦労しながらベビーカーを押している母親のためにドアを開けておくこと、スターバックスの列に並んでいたら目の前に割り込んできた男を肘で付いてやりたいという衝動に抵抗すること、などなど。別の種類の道徳判断はもう少し意識される。暗がりのなかで募金用のカップを揺らしている男に対して金を渡すかどうかを判断する時などだ。人を助けたいという欲求、危険に対する恐怖、そして自分の財布の中身に応じたコスト-ベネフィット分析…身体的な反応と理性的な推論の全てが、意識的な認識の下で渦巻くことになる。
法律や警察、神の命令・経典・説教などによって善と悪を規定する宗教的伝統などを用いて、社会は道徳的に賞賛される選択肢へと人々を駆り立てる。しかし、道徳とはそれぞれの人の頭の中にあるのだ、と最終的には言われる。もちろん、合理的な思考は、私たちが道徳について判断するときに役割を担っている。だが、私たちの持つ道徳の指標は、嫌悪感・好み・恐怖などの感情の持つ力にも強く影響されている。
あることが正しいか不正であるかを判断するときには、主観的な感情は考慮されるべきであろうか?この問題について、哲学者たちは何千年も議論してきた。ある哲学者たちはきっぱりと言う。感情は、友達や家族に対する愛情に代表されるように、私たちの人生に意味を与えるもののなかでも極めて重大な部分を担っている。そして、道徳においても感情は指導的な役割を果たすべきなのだ。別の哲学者たちは、きっぱりと否定する。冷静で公平な合理的思考だけが、判断を下すための唯一適切な方法なのである。感情 VS 理性…私たちが知っているなかでも、最も古くてそして最も壮大な対立である。
現代科学の道具を使い、道徳の意思決定という名のスープに混ざった材料を分けることはできるだろうか?…つまり、脳の中を観察することによって感情と理性とが実際のところどのように働いているかを理解して、昔からの哲学的な問題に新しい光を当てることはできるだろうか?道徳認知学という分野や、社会心理学・認知心理学・行動経済学・神経科学を合わせた分野横断的な研究が、上述したような試みをやり始めたところだ。特定の問題に対処するときに人々がどのような行動やパフォーマンスをするかを調べるために、道徳心理学者たちは2000年代の初頭から様々な実験を設計してきた。実験にはfMRIが併用されてきた。通常なら隠れて見えない脳の活動を感知することで道徳的な思考の構造を明らかにしようとしてきたのだ。
この分野のパイオニアの一人が、ハーヴァード大学の心理学教授であり哲学者でもあるジョシュア・グリーンだ。2001年から、グリーンは伝統的だがどぎつい思考実験と脳画像診断を組み合わせた研究を行っている。その思考実験とは「トロッコ問題」、スイッチを押すか押さないかや男を歩道橋から突き落とすか突き落とさないかを選択して、1人の人間を死なせるかあるいは5人を死なせるか、という問題だ*1。グリーンが行った上記の実験やその後の新しい実験は、私たちが倫理に関するトレードオフを行う際に直感はどのような役割を担っているのか、ということを解明するのに役立つものだ。そして、他の種類の判断が影響されるバイアスと同様のバイアスに道徳的な判断も影響されている、ということをグリーンの実験は明らかにしたのだ。
道徳認知の研究が道徳における感情の役割をどのように明らかにするのか(科学的に、そして哲学的にも)、私はグリーンにインタビューした。以下は、私のグリーンとの対話の内容を少しばかり編集して圧縮したものである。
インタビュアー:ある人が判断を下す際には、正しさや不正について人間が持っている直感が非合理的な影響を与える、ということをあなたの研究は明らかにしました。道徳に関する直感が私たちを惑わせて間違った判断を下させる可能性があるとしても、まだ道徳に関する直感は有益であると言えるのでしょうか?
グリーン:ええ、全く有益であると言えます。私たちの感情や身体的な反応が、生物学的進化・文化的進化・そして私たち個人の経験を通じて身に付けられてきたのは、それらの感情や反応が過去には私たちに益をもたらしてきたからです…少なくとも、特定の基準では益と言えるものをもたらしてきました。その基準を私たちが是認できるとは限りませんが。私の考えとは、感情や身体的な反応の全てが悪いということではなく、現代に生きる私たちが直面する問題を解決するための能力を感情や身体的な反応が持っているとは限らない、ということです。ここでいう現代の問題とは、文化の違いのために人々の意見が一致しない問題、テクノロジーによって生じた新しい選択肢や問題、などなどのことです。
インタビュアー:あなたは、道徳的についての意思決定の過程には2種類の思考が組み合わされている、と説明しています。スローで意識的に調整する必要のある、ルールに基づいた思考である"マニュアル"思考と、ファストで意識を要さない感情的なものである"オートマ"な心理作用の組み合わせです。この人間の思考についての"二重過程"理論は、どれだけ普及しているのでしょうか?
グリーン:調査した訳ではないですが、道徳に限らずすべての種類の意思決定について書かれた論文で、支持するにせよ批判するにせよ"二重過程"について言及していない論文を探すのはかなり難しいでしょう。『ファスト&スロー』を書いたダニエル・カーネマンや、その共同研究者のエイモス・トベルスキーのおかげです。"二重過程理論"は判断や意思決定についての理論のなかでも支配的なものとなっていますが、この理論を批判する人もいます。一部の人々、特に神経科学を研究している人は、二重過程理論はあまりにも単純化され過ぎていると考えています。脳について研究している批判者たちは、脳とは複雑であることを認識しています。脳の活動とは動態的で相互作用的であると認識しているので、意思決定や判断の回路が二つだけしかない訳がない、だから二重過程理論は間違っているのだと主張します。しかし、私からすれば、説明の仕方や特異性のレベルが違うだけであるように思えます。二重過程理論の基本的な考え…判断や意思決定をする際には自動的な過程と調整の必要な過程の二つがそれぞれ別個の役割を果たす、という考えそのものを再検討する必要を感じさせるほどの証拠には、まだ私は出会ったことがありません。
インタビュアー:あなたが説明しているような神経のメカニズムは、どのような種類の意思決定にも存在しているものですよね? …つまり、走ってくる電車から人々を助けるために男を橋から突き落とすかどうかを判断するときにも、靴を買いたいという衝動を抑えようとしている時にも、脳は同じように反応している…感情的な反応と、それよりも計算されたコスト - ベネフィット分析とを計りにかけているんですよね?
グリーン:その通りです。私が説明しているようなメカニズムは、道徳判断に限定されたものでは全くありません。
インタビュアー:そのことは、道徳とは特別で際立ったものだという考えに対して、何か示唆することはありますか?
グリーン:もちろんです。過去の10年間〜15年間における神経科学からの道徳の研究がもたらした最も明白な教訓です。つまり、少なくとも我々が理解している限りでは、他から区別された道徳のための機能は存在していないのです。私たちに観察できるのは、全く同じ行為をしている時にもその行為をする文脈によって脳内の違った箇所が反応する、ということです。道徳に特化した神経回路は存在しませんし、脳の中で特に道徳のための部位がある訳でもありませんし、道徳に独自の思考というものもありません。道徳的思考を道徳的思考たらしめるのは、その思考をしている人の脳内で起こっている機械的なプロセスではなく、その思考が社会の中でいかに機能しているかであります。道徳的思考が社会の中でどのような機能を演じるかについては、私や他の多くの人が、協力であると考えています。通常なら利己的である個人たちを、他の人たちと共に生きて働くことで得られる利益へと導かせる訳です。
インタビュアー:脳の中には特に道徳に特化した部位は存在していない、という考えは直感に反するように思えます。特に宗教的な文脈における道徳の神聖性や神性との関係をふまえると。そのような多目的な機能による説明は正しく感じられない、と主張する人からの反対を受けたことはありますか?
グリーン:ええ。道徳は脳内でも特別なものである、と人々はしばしば推測します。実際、初期の研究には、道徳的な思考とそれに似ているが道徳的ではない思考とを比較して考える研究も多く存在していました。同じような研究は現在でもある程度は行われていますが。そのような研究者たちは「ほら、ここに道徳についての神経的な相互関係があるぞ」と主張したものです。ですが、振り返ってみると…ある道徳な問題と道徳的ではない問題を比較して、そこに何か違いを見つけたとしても、それは道徳が特別な種類の認識に関わっているからではありません。もっと初歩的なところ…何について考慮しているかという文脈によって違いが生じているのです。
インタビュアー:私たちが積極的な行動をしたことによって生じた危害に対しては、なにかを行わないという消極的な行動の結果として生じる危害に対してよりも多くの道徳的な責任がある、と倫理学者たちは論じることが多いです。医者は患者を死ぬがままに任せることは法的に許されているが、終末期の患者の生命を積極的に終わらせることは、例えその患者が求めているとしても許されない、というのが具体列です。あなたは、このような "作為ー不作為の区別"が頻繁に主張される理由の大部分は、私たちの心理の仕組みから付随的に生じた特徴に由来しているかもしれない、と論じています。あなたのこの考えは、なにか影響をもたらしていますか?
グリーン:時には、他の人たちも私と同様の指摘をしてきました。例えば、倫理学者のピーター・シンガーは、彼が行為そのものについての主要ではなく付随的であると考えている特徴(訳注:作為か不作為であるか)よりも、その行為がもたらす結果の方に注目すべきである、と論じています。彼は、生命の神聖性よりも生命の質の方に注目すべきだと論じています。生命の神聖性という概念は、誰かを死ぬがままに任せることは許されるが、積極的に誰かの生命を終わらせることは、たとえ当人が望んでいたり当人の生命の質がほとんど無くなっていても許されない、ということを意味します。そして、これらについて神秘主義的に考えるのではなく、結果についてより実質的に考えて、人々に自分の生命について自分自身で決定させることを認めるべきだという主張は、生命倫理に大きな影響を与えたと思います。そして、私の研究は、このような主張への支持を新たに与えるものであると思います。
インタビュアー:道徳的な問題について自分たちは感情ではなく理性を用いて解決している、と哲学者たちは誇ってきました。ですが、あなたは著書『モラル・トライブズ』のなかで、理性の支持者のなかでも最も象徴的な存在であるイマニュエル・カントの議論の内実を効果的に暴いています。カントの議論の多くは、彼自身が暮らしていた文化に由来する感情や直感を難解な言葉で正当化したに過ぎない、とあなたは書いています。カントの主張のなかであまり有名でないものには、現代ではその結論を真面目に受け止められないような主張…例えば、マスターベーションは「自分の体を手段として使用する」から道徳的に不正である、という主張…がありますが、カントの有名な議論(訳注:人権についての主張など)も、マスターベーションについての議論と根本的には変わらない、とあなたは主張しています。これについて、人々はどのように反応しましたか?
グリーン:お察しの通り、私の議論をまったく気に入らない哲学者たちもいます。ですが、一部の人々の考えを変えることはできたとは思いたいです。私が著書のなかで書いているような議論や主張に初めて直面するが、読む前から既に特定の立場には立っていなくて、そして科学を理解できる人なら、私の議論を読んでこのように言います。「うん、たしかに筋が通っているね」と。
インタビュアー:自分は感情の合理化・正当化(rationalization)をしているのではなくて、真正に道徳的な推論を行っているのだ、ということを判断するためにはどうすればいいでしょうか?
グリーン:判断する方法の一つとして、感情や身体的な反応としては気に食わない結論を自分自身が真剣に受け入れられているかどうかを確認する、ということがあります。自分は自身の身体的な反応と闘うことができているか?ということを確認するのです。もし自分が身体的な反応と闘うことができているのなら、そのことは、自分は感情を合理化しているのではなく実際に真剣に考えることができているのだ、ということを明白に示しているでしょう。
インタビュアー:哲学から心理学まで、あなたが研究したり学んだ全てのことをふまえると、賢明さや知恵とは具体的には何を意味していると考えますか?
グリーン:賢い人間とは、熟練の写真家がカメラを調整するのと同じように自分の考えを調整できる人のことである、と言えるでしょう。オートマ設定だけでなく、マニュアルモードも上手に扱えるようでなければいけません。ですが、それだけではなく、いつオートマを使うべきでありいつマニュアルを使うべきであるかということを心得ている必要もあります。さらに、どのような状況でどのような特定の種類のオートマ設定に頼るべきであるか、ということも心得なければいけません。
どのように行動するかということについての直感を、あなたは人生を通じて身に付けます。しかし、人生において状況が変わることもあります。ある時点では通じたことが、別の時点では通じなくなる場合もあります。ですが、どのような時には現在の直感に逆らって新しい行動に挑戦するべきであるか、ということについての高次の直感を身に付けることもできます。完璧なアルゴリズムなんて存在しません。しかし、多層な度合いの抽象演算子のそれぞれにおいて、硬直性と柔軟性をそれぞれ適切な度合いで持っている…賢明な精神とはそのようなものである、とは言えるでしょう。
インタビュアー:特定の種類の内観的なテクニックが持つ可能性については、どのように考えますか? …ここで私が念頭に置いているのは、仏教の教えに由来する、瞑想やマインドフルネスのテクニックのことですが。これらのテクニックは、自分自身の道徳に関する自己認識を向上させる手段になると思いますか?
グリーン:それは興味深い質問ですね。…瞑想をしているとき、あなたは自分自身の心の機能を観察しています。熟練の写真家がカメラの扱い方を習得するのと同じように、あなたは自分自身の心を扱い方を習得します。つまり、単に思考しているだけではなく、どのように思考するべきかということについて思考しているときに、あなたは高次の技術を身につけているのです。そして、あなたは自分自身の低次の思考を高次の思考で監視します。…このような階層的な思考を統合するわけです。
上述したようなことについて研究している人から、特定の種類の瞑想なら同情心や他人を助けるための意志を増すことが実際にできる、と聞きます。とても説得力があると私も思います。例えば、タニア・シンガーという研究者はこのことについて最近研究しており、その研究はとても興味深くて注目せずにはいられません*2。私はこの話題の専門家ではないのですが、私が尊敬する科学者に聞いたことから判断すると、適切な種類の瞑想であれば、大半の人が道徳的向上であると考えるような変化をあなた自身にもたらすことが可能である、という主張は妥当であるように思われます。