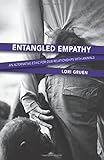倫理学の入門書などにおいて義務論や帰結主義とならぶ規範倫理として徳倫理学が紹介されるときは、「〜主義」を否定して「中庸」を強調する、どちらかとえいばマイルドで当たり障りのない主義主張して紹介されることが多い。しかし、この本ではプラトンやアリストテレスなどに代表される古代ギリシアの哲学者たちが実際のところ「徳」や「幸福」について何と語っていたかが紹介されつつ、その主張の過激性やエリート主義性を明らかにする。何よりの特徴は、現代の民主主義社会で生きていたはずの著者が、古代の徳倫理学のエリート主義性を高らかに肯定しているところである*1。
この本は3部構成になっており、第1部では古代の「気概の倫理」がキリスト教による平等主義とそれを前提とした「義務の倫理」に取って代わられた経緯が綴られる。いかにもニーチェの『道徳の系譜学』を思わせる内容だ*2。第2部では、ソクラテスからアリストテレスに至るまで、古代ギリシアにおける「気概の倫理」概念の発展の思想史が概略される。そして、第3部では「義務の倫理」と「気概の倫理」概念の詳細が対比されつつ、「気概の倫理」における「誇り」や「幸福」という概念について詳らかにされるのである。
先述した通り、徳倫理学といえば「中庸」が強調されることが多く、J.O.アームソンの『アリストテレス倫理学入門』でもそうだったし、ジュリア・アナスの『徳は知なり』でも現代の我々の生活にも通じる幸福論として徳倫理学が紹介されていた。だが、この本の著者であるテイラー氏の手にかかると、徳倫理はかなり違った相貌を見せるようになる。
たとえば、アリストテレスの倫理学については以下のように書かれている。
…古代の哲学者のほとんど誰も疑問に思わなかった「ある種の人々は他の人々より本当に優れており、したがってより大きな値打ちがある」という信念がなかったとしたら、アリストテレスの重要な特徴が失われてしまうであろう。まことに、これこそ「気概」という観念自体に内在しているものなのである。アリストテレス以上に気概の倫理を見事に表現している道徳哲学などないのだ。
古代の道徳学者たちが考えていたように、道徳哲学の目的が「人間の自然本性」についての理想を描き、その実現への道筋をつけることであるとするなら、「賢者も愚者もみな等しく理想に到達できる」と想定するのはほとんど不可能である。事実はその反対であって、「少数の人を除けば、どのような人でもいずれは理想に到達できる」などということはなさそうだ。だから、理想を実現した人は理想を実現できなかった大多数の人々よりも文字通り「より善い」のである。このような前提なしに古代の道徳哲学者たちを理解しようとするのは、義務の観念を削除してカントの道徳哲学を理解しようとするようなものである。
このようなエリート主義、すなわちアリストテレスが価値ある人々とそうでない人の間にはっきりとした不公平な区別を設けたことは、決して気まぐれではないし特異な嗜好でもない。これと同じようなことは、「奴隷と友人になれるか」ーーアリストテレスによると奴隷とは「生きた道具」にすぎないーーという難しい問題をやや苦心しながら論じた箇所で繰り返されているし、アリストテレスが真の友人関係は比較的少数の「善き」人々、つまり「個人の卓越」の厳格な水準に達した人々の間でしか成り立たないとしている箇所にも見られる。まさしくエリート主義はアリストテレスの倫理概念全体に固有なものなのである。
仮にアリストテレスに対して「経験上はそうではないが、全ての人間は本来的に、あるいは自然本性によって、平等である」と仮定するよう求めたとすれば、彼にとって最も基本的な倫理の諸問題は存在さえしなかったであろう。アリストテレスにとって倫理の役目とは「人間の間の不平等を助長し増大させること」、つまり「自然本性的により善き人々が、他の人々よりも個人的価値をできるだけ高められるようにすること」に他ならなかった。
(p.110 - 111)
また、「幸福」という概念について、古代ギリシアの哲学の主張に基づいた著者自身の見解を論じる章からも引用しよう。
子供、白痴、未開人、さらには動物にも快苦を経験する能力が完全にある。しかし彼らのいずれも、本書における意味で「幸福」になることはできないのである。確かに「幸福な子供」とか、「幸福な知恵遅れ」と言うのは正しいのだが、そうした事例には注意する必要がある。
例えば「幸福な子供」とは、良い生活をしている子供である。言い変えれば、「しあわせ」の条件に合致している子供のことである。これらの条件には愛情、信頼感と安心感、愛情のこもった躾などが含まれている。実際こうした恵まれた条件にある子供は不機嫌でも不安でも憂鬱でも陰気でもない。これは明らかに幸福を意味するから、その意味では「幸福な子供」と言えるのかもしれない。
しかしながら、やはりこの子は哲学的に重要な意味においては「幸福」ではない。すなわち「何かを実現している」とか「最高の個人的善に恵まれている」という意味では「幸福」ではないのである。この種の「幸福」は子供の場合は、将来に期待するしかない。「幸福な子供」という場合の「幸福」とは、確かに現実的なものであるから大切ではある。だが所詮は「気持ちいいい感じ」、つまりある種の健全な生活を送る時に感じる「感覚」の域を出るものではないのである。もちろんそれはそれでよいことなのだが、道徳的生活の目的である「偉大な善」ではない。偉大な善を獲得するには通常、人生の大半の時間を要するのである。
(p.183)
つまり、誰しもが倫理的な人間になれる訳でもなければ価値のある人間になれる訳でもないし、幸福への道は万人に平等に開かれているわけではない、ということだ。
「気概の倫理」におけるこれらの主張は多くの人にとって不快感や違和感を抱かせるものだろうし、私としても素直に肯定できる主張ではない。しかし、テイラー氏によると、それは現代の私たちがキリスト教的を源泉とする民主主義的で平等主義的な「義務の倫理」の考え方に慣れきってしまっているから、ということになるのだろう。ニーチェによればそれは強者を妬んで強者の足を引っ張ろうとする弱者のルサンチマンであるし、本書の中でも(ニーチェが影響を受けたことで有名な)カリクレスの主張が紹介されている。
カリクレスに言わせれば、大多数の人は弱い。これが意味するところはまさに、自らを他人よりずっと善く際立たせてくれる知性や機転や勇気などの自然の賜物を大部分の人はあまり持っていないということである。大半の人は概して相当に無知で、愚かで、鈍感である。要するに弱い、つまり劣っている。この相対的な劣等性は彼らの心に、自らの幸せの心配だけでなく、当然ながら劣等感も惹き起す。彼らは自分よりも「善き」人々に利用されることを恐れる。彼らがこう感じるのも正しい。というのはカリクレスによれば、善く高貴な人の数は常に比較的少ないが、彼らは大衆の取るに足らないちっぽけな利益のためではなく、自分自身の利益増進を目指して統治しようとするであろうし、またそうすべきだからである。
かくして、この事実を受け止めて弱者たちは「道徳規則」という形で優れた者たちに制約を課す。そして、この手の道徳のまさに第一原則こそ「全ての人間は平等である」ということなのである。これは明らかに偽であるものの、多くの弱者に「自分は真に有徳な人と同じくらい善い」と感じさせてくれる原則である。
(p.72-73)
テイラー氏によると、現代の倫理学は「道徳的に正しい」「道徳的に間違っている」という概念を云々している時点で、的外れなのである。本来の倫理学とは「徳とは何か」「卓越した人はどういう人であるか」ということを問うべきなのであり、何が正しくて何が間違っているかということは観衆が決めることなのであって哲学が関わりづらう事柄ではないのだ。しかし、宗教の登場によって「正しさ」や「不正」という概念が慣習を超えた普遍的なものであるかのように見なされるようになった。そして、「理性」によって正や不正を明らかにすることができると論じたカントにせよ、「快」を与えるか奪うかという観点から行為の正や不正を決定することができると論じたミルにせよ、本人たちは宗教的に基づいた思考を捨てて論理的に思考しているつもりであっても、「正しさ」や「不正」を論じようとしている時点で宗教の影響から脱していないのである…と、テイラー氏は論じる。
はっきり言ってこのような思想史的な議論やそれこそニーチェのような「系譜学」的な議論が的を得ているとは思えない。カントやミルに対する「キリスト教を捨てているつもりでもキリスト教の影響から脱していない」という批判はお粗末な西洋文化論にありがちなものだし、反証可能性のない主張だろう。そもそも、キリスト教の影響が希薄であるはずの日本人や他の文化圏の人たちでも「道徳的に正しい」「道徳的に間違っている」という概念が必要だと思う人は多くいるだろう。近代以降に「正」や「不正」の概念の重要性が増したのは、社会の民主化や平等主義化が影響を与えただけでなく、啓蒙主義の時代を経て科学的思考や理性的思考が古代よりも発達したからだと論じることができる*3。「訳者あとがき」でも指摘されているように、古代ギリシアでもストア派の扱いはこの本では非常に手薄なのだが、そのストア派は普遍主義的な発想を持っていたのであ*4。そして、社会制度が複雑化したりグローバル化などで異なる文化圏からの様々な人々が関わるようになったり資本主義の発展で経済活動の範囲や領域が活動したりなどなどな現代社会では、慣習によらない方法で道徳的な「正」や「不正」を論じる必要性はますます増しているのだ。
…とはいえ、私としては、「民主主義や平等主義が道徳に関する人々の考え方を侵食している」という著者の批判には共感できるところもなくはない。
たとえば、「誰もが幸福になれるわけではない」とまでは言えないが、誰もが幸福について語る資格があるわけではない、とは私も思っている*5。科学や政治や経済などの「公」的な専門知の分野においては「民主主義や平等主義が、専門的知識が必要とされるはずの分野に対しても知識のない人が口を出せるように錯覚させてしまった」という嘆きは珍しくない*6。そして、幸福や人間性から趣味や嗜好などの「私」的な領域においても、誰しもの意見が平等に尊重されるべきではない、と私は思っている。人生経験が豊富であったり人生について誠実に思考している人の意見はそうでない人の意見よりも価値があるだろうし、それは趣味や嗜好などにおいても同様だ。ネット言説におけるサイゼリヤやストロングゼロの過剰評価については、先日の記事で論じた*7。そして、「低質」とされがちな嗜好への賛美が集まる一方で、「上質」とされる嗜好の価値に疑問が投げかけられる風景もよく見られる*8。この風潮の背後には民主主義や平等主義のみならずルサンチマンも存在することは明白であるように思えるのだ。
…しかし、古代ギリシア人やテイラー氏が理想とするような「卓越した人間」が現代社会に存在し得るか、ということにはやはり疑問を抱かずにはいられない。
いくつかの徳は天賦の才能である。その好例は知性である。もちろんすぐれた「自然的知性」に恵まれていたとしても、困窮などの生活条件によってだめになってしまうこともあろう。しかし、どのような社会や環境を以てしても優れた知性を作り出すことはできない。
知性以外の「自然的徳」の例としては、器量とか体力とか創意とか精妙なものへの感受性や機転などが挙げられる。もちろん、これらの徳を初めから完成させた形で具えて生まれてくる人はいないが、何人かの人はそうした徳へと向かう能力を具えて生まれてくるし、ごく僅かではあるがこれらの徳のいくつかを非常に高度に発達させる能力を生まれながらに持っている人もいる。こうした人々はまさしく模範的人物であり、偉大な才能を欠いている大多数よりも生まれながらに抜きんでている人々である。簡単に言えば、このような(めったにいない)人々こそ古典ギリシア的な意味で真に徳のある人々なのである。
ここで大切なことは「知性や体力のように自然が与えたに過ぎず、自分では選べない能力によって人を賞賛するのはおかしい」と反対したくなる気持ちを抑えることである。この反対意見は徳についての我々の考えとギリシア人の考えをすっかり混同している。ギリシア人にとっては徳には選択や意志との必然的結びつきなど少しもなかった。そのような考えは本質的にキリスト教のものであり、我々はそちらを受け継いだのである。だがそれはカリクレスの時代の思想家たちにはまったく異質なものだった。
(p.71)
さて、現代の私たちがキリスト教の考え方に影響されていることを仮に認めたとしても、私たちの考え方は自然科学や社会科学が明らかにした様々な事実からも影響を受けているということを否定することはできない。つまり、生得的な能力についての遺伝学の知識、幼少時の環境や通った学校などが人格や能力の形成に与える影響についての教育学や心理学の知識、階級の再生産についての経済学の知識や階級と文化資本の関係にする社会学の知識などなどだ。
これらの知識を得れば得るほど、「卓越した人間」という人間像を素直に受け取ることはできなくなる。「徳」とされる能力の多くが遺伝的であることや、その能力の開花には環境や教育が重要であることは古代ギリシア人も多かれ少なかれ気付いていたかもしれない。しかし、現代の我々は、徳を開花させやすい環境や教育が得られるかどうかが階級によって左右されることも知っている*9。そして、どのような性質が「徳」とされたりどのような振る舞いをすることで「卓越した人間」とされたりするかは多かれ少なかれ社会的に構成されるものであるということにも気付いているし、その社会的公正には階級的利害も関与しているだろう(つまり、上流階級の行う振る舞いや上流階級の人々が持つ性質が事後的に「有徳」とされる、ということだ)。…このような知識を前提にすると、やはり、「自分とでは選べない能力によって人を賞賛するのはおかしい」と反対したくなるものだ。そして、このような不平等は道徳的に防いであり是正するべきである、と「義務の倫理」的な主張をしたくなるものである。
また、上記のものとは全く別の側面からも、古代ギリシアにおける「卓越した人間」像が現代では説得力を持たない理由がある。というのも、現代のような社会では、職業や実績などを通じてその人が「どのような行為をしている(行為をした)人間であるか」を無視してその人が「どのような人間であるか」を評価するのは困難になっているからだ。…本書によると「徳」は「能力」とほぼ同義語な側面があるようだ。となると、有能な人間が卓越した人間であるということになるかもしれない。だが、現代の社会では、「能力を発揮する」ことは、大半の場合には「お金を稼ぐ」「他人からの承認を集める」「より良い社会的地位につく」などなどにつながってしまう。だが、本書でも指摘されているように、お金を無心に稼いだり他人かの評価に右往左往することは卓越した人間のやることではない。…有能な人間なら起業家や政治家、官僚や芸能人などになるかもしれないが、彼らのほとんど全員が我々の理想になるような「卓越した人間」からは程遠いことは、彼らの言動や彼らについての報道を見聞していたらわかることだろう。
この本のなかでも、「卓越した人間」とはどういう人であるかについてはくどくどと細かく描写されている。だが、どこに行けばそのような人に出会えるのか?それは教えてくれないのである。