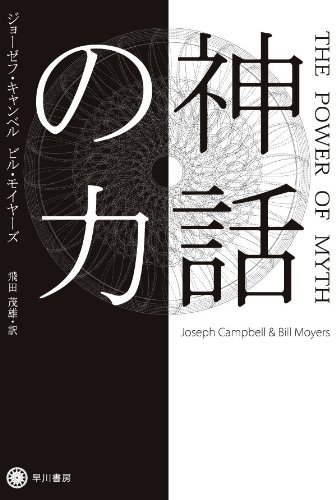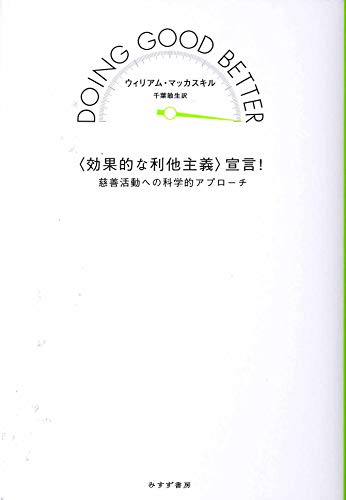『Virtue Signaling』の書評で書いたようにわたしはジェフリー・ミラーは文筆家としてはあまり好ましく思っていないところがある。『恋人選びの心』も、「人間に特有の知性や言葉や芸術性やユーモアはすべて性淘汰の産物として進化してきた」という理論でなんでもかんでもされており、「牽強付会」という感が付きまとう。
とはいえ、ミラーが提示しているのあくまで仮説であり「この仮説を使えばあんなこともこんなことも説明できますよ」というデモンストレーションとして、批判は承知のうえで、あえていろんな物事について「性淘汰とシグナリング」の理論を当てはめて説明しているのかもしれない。
この本の1〜3章では、ダーウィンによる性淘汰の発見にまで遡りながら、ダーウィン以後の進化理論では自然淘汰ばかりが強調されて性淘汰が無視されてきた、という歴史が振り返られる。また、性淘汰やシグナリング理論、ランナウェイ進化などの考え方が解説される。
そして、本番となる4章以降では、人間のさまざまな特徴が「性淘汰」によって解説されることになるのだ。
面白いと思ったところをいくつか紹介しよう。
性淘汰は、性的不誠実に対して二段階の防衛を用意している。一つは大恋愛であり、もう一つは親密な性的コミットメントである。大恋愛は、他の誰でもないたった一人の相手に向かって、すべての求愛努力を強力に向けさせる。少なくとも数週間から数カ月にわたって、これは不誠実を抑制する。大恋愛が性的な魅力であることは言うまでもない。これは、それ以外の点で魅力的でない人物を結婚へとこぎつかせることはできないかもしれないが、他のすべてが同じだとすると、明らかに恋人選びでは評価されている。愛は性淘汰によって進化したが、とりわけ、誠実さの信号として進化したのである。
(p.469)
上記は、「ロマンティック・ラブ」の進化的な説明であると言えるだろう。そして、ロマンティック・ラブを「イデオロギー」として軽率に退けようとする言説や、「恋愛という考え方は西欧由来であり、近代化するまで日本には恋愛というものは存在しなかった」という言説に対するいい反論になると思う。
わたしが大学の学部生だった頃、「世界中のまったく異なる文化圏におけるフィクションや物語に、なぜ共通点が多く存在するのか」ということが授業で説明されるときには、ジョーゼフ・キャンベル的な「神話学」ばっかり聞かされていた。当時から、わたしにはキャンベルの議論は胡散臭く物足りないものであるように思えていた*1。
また、文学研究者たちが「恋愛は西欧由来」という言説に考え方を縛られてきたとすれば、かなり多くの読み違えが発生してきたということになるはずだ。「ある物語の構造を多くの人が面白いと感じるなら、それはなぜか」「なぜ、ある特定のテーマは人を惹きつけて、それについての物語が多く書かれているのか」ということを論じるうえでは、心理学的・進化的な解釈は欠かせないように思える*2。
性淘汰がなければ、人間が慈善を行う傾向は、ずっと進化的な謎としてとどまっただろう。
(……中略……)
慈善によって、与え手から受け手に資源がどれほど委譲されるかということに、多くの人々があまり注意を払わないのは不思議なことだ。
(……中略……)
人間の慈善のもう一つの特徴は、寄付者が寄付したことを示す何らかのしるしをもらうことができ、それを公的に表示することができるということだ。
(……中略……)
人間の慈善に関する、これらの奇妙な性質をどのように説明したらよいだろう?これが、血縁淘汰や互恵性から出ているとはとても思えない。また、真の利他性を身につけさせようという社会化の結果とも思えない。そうではなくて、これらの多くは、慈善もまた別の形の無駄に満ちた見せびらかしであることを示している。慈善の本質が、他者に真の利益をもたらすことではなく、寄付者にコストをかけさせることにあるのだとすれば、人々がなぜ慈善事業の効率のよさに注意を払わないのか、金を寄付するべきときにどうして時間を寄付するのか、などといったことが理解できるようになるだろう。慈善への寄付が、信号として有効であることを宣伝しなければならないのであれば、寄付者がどうしてその善意を表示するための小さなバッジをもらうのかも理解できるし、慈善事業が強力なブランド名を作り出すためにこれほどの大金を基金集めに使うのはなぜかなども理解することができるだろう。慈善もまた、それを認識してもらい、記憶に残っていてもらわなければならない信号であるとするならば、なぜ人々が、本当に必要性が高いにもかかわらず地味な団体よりも、有名ですでに巨額の基金を持っている団体に寄付するのかということも理解できる。慈善は求愛誇示であるとすると、慈善が流行のサイクルにのっていることも理解できる。このことは、とくに、若くて独身の寄付者の間で明らかである。私たちのほとんどにとって、慈善は化粧品のようなものだ。
(p.452 - 457)
なぜ大半の人々は「効果的ではない利他主義」を実践してしまうか、ひいては道徳的な性質全般についての、性淘汰に基づいた説明である。
人々が慈善行為や利他的行為の「効果」を気にしないこと、それよりもそれらの行為を「見せびらかす」ことの方が重要なのだ、という指摘については考える余地もあるかもしれない。……とはいえ、たとえば「効果的な利他主義」について書かれた本を読んでみると、人々が「効果的ではない利他主義」を行ってしまう理由は、性淘汰とは関係のないヒューリスティックスやバイアスによって説明されている*3。性淘汰の理論にかかると、慈善や道徳に限らず、勇気や知性など、わたしたちが「徳」であるとみなして望ましく思っている性質のすべてが、「異性に対するアピール」に還元されてしまう。これは、理論の長所ではなく欠点だと見なされるべきだろう。
進化的な視点から言えば、芸術家が直面しているもっとも本質的な挑戦は、適応度の低い競争者には作れないような何かを作ることにより、彼らの適応度を誇示し、それによって自分を社会的にも性的にもより魅力的に見せることである。この挑戦は、視覚芸術だけにとどまらず、音楽、物語、ユーモアその他、本書で論じたさまざまな行動のどれにおいても同じである。適応度指標の原理は、誇示の仕方が異なる領域でも似通っている。だからこそ、美学的な原理の大多数は同じなのである。
(……中略……)
美は真実を伝えている。しかし、それは、私たちが考えるようにではない。審美的重要性は、人間の条件一般についての真実を提供しているのではない。それは、芸術家本人という、特定の人間の条件についての真実を提供しているのだ。芸術の美的な性質は、その芸術家の技巧の表出としておもに意味をなすのであって、啓蒙、宗教的霊感、社会的な批評、精神分析的発露、政治的革命などを伝える媒体としてではない。プラトンとヘーゲルは、彼らが哲学なら生み出せると思っていた真実と同じ真実を芸術は提供することができないといって、芸術をおとしめた。彼らは、芸術の意味を誤解したのである。生物学的適応度の誇示として進化した媒体に、抽象的哲学的真実を伝えるようによく適応しろと言っても、それは不公平というものだ。
(p.397-398)
芸術家や小説家はモテるのに学者や批評家はモテない理由、芸術系のサークルが性的に爛れがちな理由の説明になっていると思う。もう少し深く考えれば、大御所の芸術家がハラスメント体質になりがちな理由も説明できるかもしれない。
また、美的感覚の進化心理学的解釈は、ブルデューのような社会学者や、美学者たちによる芸術論とある面では一致していて、ある面では矛盾しているように思える*4。芸術や美を鑑賞する感覚が進化的に身についたものであれば、「文化資本」とか芸術に関する前知識がなくても、ある作品の芸術的良さが理解できるはずだろう。一方で、"高度な"芸術はあえて進化的な美の感覚からは乖離して作られており、理解するのに知識や前提を要求することで、庶民とエリートを分別する機能を担わされている……という考え方をすることもできるかもしれない。
私たちの恋人選びのメカニズムが似たようなものであり続ける限り、先史時代に恋人選びで形成された性質は、今日でも性的に魅力的なはずである。さまざまな文化や歴史時代を通じて、ある身体形質が性的魅力だと見なされていれば、その形質はおそらく人間の進化の過程において、ずっとそう思われてきたのだろう。たとえば、女性の乳房と臀部が性的魅力であることは、異性愛者の男性のすべてにとって主観的には明らかなことであるが、明らかだということは、これらの形質が男性の恋人選びで生じてきたことのよい証拠であろう。世界中で、個体が自分を魅力的に見せようとするときには、同じ身体形質が強調され、個体が性的な注目を受けたくないときには同じ身体形質が隠され、性的な犯罪に対する罰として、同じ身体形質が切断される傾向があるのだ。
(p.320)
上記は、「性」や「好み」に関する社会構築論を真っ向から否定している一節だ。
性淘汰の観点からすれば、クリトリスは、時間をかけたエネルギッシュなセックスに必要な肉体的適応度と、女性が何を欲していて、どうすればそれを提供できるのかを理解するのに必要な心的適応度との両方を備えていることを示した男性にのみ反応すべきである。選り好みの激しいクリトリスは、女性が本当に相手の男性のからだと心と性格のすべてに強く惹かれ、その男性が自分の魅力と適応度とを正しい刺激によって示したときのみオルガズムを生み出すべきなのである。
(p.336)
女性は男性の「からだ」だけでなく「心」と「性格」を選り好みしている、という点は要注目だ。
進化心理学による男女論というと、「女性は肉体的で暴力的な男性にオスとしての魅力を感じる」的な言説がよくなされる。また、たとえば恋愛工学では「男性の稼得能力や社会的地位に、女性は魅力を感じる」ということが強調される。たしかにそういう側面はあるのだろうが、それだけではなく、女性は男性の誠実さとか気遣いとかもちゃんと見ているのだ。
リチャード・プラムの『美の進化:性選択は人間と動物をどう変えたか』でも、人間やほかの動物が異性のどのようなポイントに対して魅力を感じるかは、性淘汰によって実に多様で幅広くなっている、ということが論じられていた。
恋愛工学的な男女論は「生存と繁殖」を強調する自然淘汰の観点ばかりを強調するから、皮相で一面的な男女論になってしまうのだろう。この点では、性淘汰の方に分があると言える。
ランナウェイ性淘汰は、脳の大きさや知能に直接働いたのではなく、高度な創造的知能の行動表現に対して働いたのだと論じることもできるだろう。こう考えると、男性のほうが女性よりも、美術、音楽、文学などにおいて作品を発表したり、富を蓄積したり、政治的地位を得たりすることを通して、自分の創造的知性を宣伝したがる傾向が強いことは、ランナウェイ性淘汰で説明できるかもしれない。この理論をもっと押し進めると、人間の文化がずっと男性によって支配されてきたのは、文化のほとんどが求愛行動だからであり、ほとんどの哺乳類のオスが求愛により多くのエネルギーを費やすことと同じである、と論じることができるだろう。男性は、女性よりも多くの絵を描き、多くのジャズ・アルバムを録音し、多くの小説を書き、多くの殺人を犯し、ギネスブックにのる妙な技をより多く行う。人口学的なデータをとると、このような行動が誇示される率には大きな性差があるばかりでなく、男性のこれらの行動の率は、性的な競争と求愛の努力がもっとも激しくなる二〇代から三〇代にピークがあることもわかる。この効果は、世界中のどこの横丁でも見られることだ。もしも、大きな音で音楽を鳴らしながら近づいていくる車があったら、それはたいてい、音楽を性的な誇示に使っている若い男性が運転する車である。
(p.115)
この説明が正しいとすれば、特にアートの世界で男女のアファーマティブ・アクションやクォータ制を実施することにはデメリットがある、と論じられるかもしれない。アートの世界に女性が少ないのは、アートの世界が女性を排除する構造になっているからではなく、ただ単にアートをやりたがる人には男性が多いから、ということになるためだ*5
。
……しかし、たとえば美術大学では、志願者も入学者も、女性の割合の方が男性の割合よりもずっと高い、ということはよく知られている*6。となると、この議論は通じない。
あるいは、アートをしたがる人には女性が多いが、アートを「誇示」したがる人には男性が多い、ということかもしれない。
*1:
*2:わたしは未読だけど、「進化心理学の観点からの文学解釈」としては、たとえばこのような本が存在する。

Madame Bovary's Ovaries: A Darwinian Look at Literature (English Edition)
- 作者:Barash, David P.,Barash, Nanelle R.
- 発売日: 2007/12/18
- メディア: Kindle版
*3:
*4:
*5:
*6: