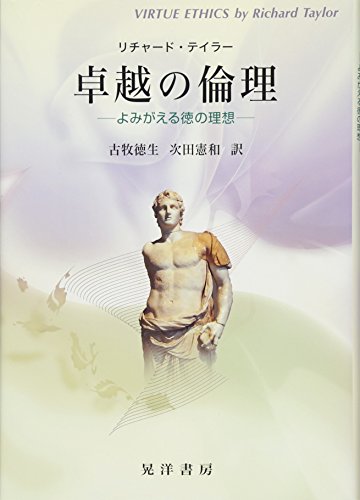『しあわせ仮説:古代の知恵と現代科学の知恵』の第10章から、仕事(労働)に関する議論を紹介しよう。
カール・マルクスによる資本主義批判は、産業革命が、職人と生産物とのあいだの歴史的な関係性を壊してしまったというもっともな主張に基づいている。組み立てラインは人を巨大な機械の歯車へと貶め、機械は労働者の効力感に対する欲求など気にかけなかった。その後の労働満足度に関する研究は、マルクスの批判を支持しているが、微妙な追加がある。1964年に社会学者のメルヴィン・コーンとカーミ・スクーラーが3100名のアメリカ人男性の職業について調査し、「職業的な自己主導性」と名づけたものが、職業の満足度の高さを知るためのキーとなっていることを見出した。複雑度が低く、ルーチン性の高い仕事に従事し、きっちりと管理されている人はもっとも高い度合いの疎外感(仕事から切り離され、無力で、不満足に感じること)を示した。変化に富んだ難しい仕事で取り組み方により多くの裁量を持つ人たちは、その仕事をより楽しむ傾向にあった。労働者は、職業的な自己主導性を有している時、その仕事により満足していた。
もっと最近の研究では、ほとんどの人は仕事に対して、労働、キャリア、天職の三つのうちのどれかのアプローチをしているということがわかった。仕事を労働と見なす人は、お金のためだけに働き、週末を夢見ながら頻繁に時計を眺め、おそらくは、仕事上よりも効力感に対する欲求を包括的に満たしてくれる趣味を追求するだろう。仕事をキャリアと見なす人は、進歩や昇給、名声といったより大きな目標を持っている。これらの目標の追求がしばしばエネルギーを与え、業務を適切に完了したいがために時おり家に仕事を持ち帰る。しかしたまに、なぜこんなに一生懸命に仕事をしなければならないのか疑問に思う。仕事が、競争のために競争をするラット・レースのように見えてしまうこともある。しかしながら、仕事を天職と見なす人は、その仕事自体に本質的に満足している。何か別のことを達成するために行うのではない。仕事を、大いなる善行への貢献や、明らかに価値があると思える何らかのより大きな計画への貢献だと考えている。仕事中に頻繁にフローを体験する。「退社時間」を楽しみに待ったり、「やった、神様、金曜日だ!」と叫びたくなったりしない。急にとても裕福になったとしたら、おそらく給料がもらえなくても、その仕事を続けるだろう。
(p.318 - 319)
マルクスが示した「労働疎外」の問題は実際にはたらく労働者のかなり多くが感じていることのはずであり、2021年の現在でも、労働に関する議論では重大なテーマとなっている。デビッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ:クソどうでもいい仕事の理論』だって、「疎外された労働」の現代風な言い換えに過ぎない。
ただし、『ブルシット・ジョブ』や植村邦彦の『隠された奴隷制』など、労働と疎外に関するマルクス主義者たちの議論は「制度」や「構造」の問題にばかり注目し過ぎる、という欠点がある。
たとえば植村の議論は「仕事による自己実現」という考え方自体を資本家たちにとって都合の良いイデオロギーであるとみなすものであった。つまり、労働者にとって仕事が「キャリア」や「天職」となり得るという考え方は、資本家たちが労働力を体良く搾取するために振りまいた幻想に過ぎない。だから、労働者は自分の仕事はあくまで「労働」であるという事実を直視したうえで、自分の心身や利益を守るためには労働へのコミットメントを避けたり場合によっては労働から逃避したりするべきである……といった議論が展開されていたのだ。
しかし、「自分のやっている仕事はキャリアや天職なんかではなく、労働でしかありえない」という考え方を抱いてしまうと、疎外の感覚から逃れることはいよいよ不可能になるはずだ。
それに、そもそも、「キャリア」や「天職」という発想はイデオロギーや幻想である、という考え方自体が疑わしいものだ。
ブルーカラーの労働者が労働と感じ、管理職がキャリアと感じ、より尊敬される専門家(医者、科学者、聖職者)が天職だと感じると思うかもしれない。その予想は多少は当たっているが、それでもなお、マルクス・アウレリウスのことばをもじって「仕事それ自身はあなたがそう見なしている以外のものである」と言えるだろう。ニューヨーク大学の心理学者であるエミー・ウェズニスキーは、彼女が研究したすべての職業に、この三つの指向がほぼすべて見られることを発見した。たとえば、病院労働者の研究では、嘔吐物を拭いたりベッド用の痰受け皿を清掃したりする、おそらくは病院でもっともランクの低い労働者である清掃員の中にも、人を治癒するという目標を持つチームの一員であると考えている人がいた。彼らは、最低限要求されていることをはるかに上回る仕事をしていた。たとえば彼らは、重病人の病室を明るくしようとしたり、命令を待つよりもむしろ、医者や看護婦の要求を予想したりした。それによって、職業的な自己主導性を増加させ、効力動機づけを満足させる労働を創り出していた。このような方法で働いていた清掃員は彼らの仕事を天職として見なしており、それを労働として見なしている人たちよりもずっと楽しんでいた。
(p. 319 -320)
要するに、仕事によって「疎外」されるかどうかはその仕事の種類や性質だけに左右されたり構造のみによって決定されたりするものではなく、本人の態度や行動などの「気の持ちよう」が大きく関係してくる、ということだ。
先日の記事でも指摘した通り、社会の制度や構造を批判するための左派的な思想と、社会の一員として活躍したり幸福で充実した生活を送ったりするための自己啓発的な思想は、相反する性質を持っている。どちらかが正確でどちらかが間違っているということではなく、問題としている物事のレイヤーや問題について論じるための視角が異なっているのだ。……だが、左派的な「構造批判」の発想に振りまわされ過ぎると、仕事に対して前向きな気を持つことが困難になってしまうものである。
「労働」を「キャリア」や「天職」とするためには、その仕事の内容が自分の性質や特徴と合っているかどうか、という問題も関わってくる(ハイトはこれを「自分の強み」と表現している)。とはいえ、一見すると自分の強みが活かせられないように思える仕事であっても、自分の強みと合致するように仕事について再解釈したり仕事への向き合い方を変えられることが可能な場合もある。
また、「天職」である仕事とは、「その仕事の内容自体に没頭できて楽しめること」と「自分の人生の意味づけに合致していること」の両方から成り立つ、「バイタル・エンゲージメント」というものを備えた仕事のことである。
自分が興味を持ったことや経験したことなどに基づきながら「自分の人生にはこういう意味がある」「自分は人生においてこういう目標を持ちたい」などといった考えを形成したうえで、自分のやっている仕事がそれにマッチしたものであれば、仕事に対して前向きな気持ちで接することができて仕事から幸福感を得ることも容易になる、ということだ。
要するに、仕事には「意義」や「やり甲斐」が必要だ、という話である。そして、バイタル・エンゲージメントは主観的な要素に左右されるものであるとはいえ、ふつうの仕事に比べて意義ややり甲斐を感じることが難しい仕事というものもある。
「良いことをする(他者に対して役だつものを生産する、質の高い仕事をする)ことが良い結果(富の達成や専門家としての向上)に結びつく時、その分野は健全である」(p.324 - 325) 。ハイトは、やり甲斐が感じられやすい健全な分野の例として「遺伝学」を挙げており、その逆の分野の例として「ジャーナリズム」を挙げている。質が良くて社会的に有益な記事を提供することは会社やジャーナリスト個人の金銭的利益とは相反することが多いために、大半のジャーナリストは質の悪い記事や社会的に有害な記事を量産する羽目になって、自分のなかの道徳的基準が破られることに苦しむのだ。
グレーバーが『ブルシット・ジョブ』のなかで並べ連ねていた「クソどうでもいい仕事」の大半も、「良いこと」と「良い結果」が結び付いていないために、その仕事をしている本人たちに疎外の感覚を抱かせる仕事であった。
しかし、グレーバーの議論は「クソどうでもいい仕事」が発生する原因をすべて「新自由主義」に押し付けたうえで、「新自由主義さえ打ち倒せば、クソどうでもいい仕事はなくなる」とアジテーションする内容であった。だが、その議論は、「ネオリベ批判」的な議論の大半がそうであるように藁人形論法的で陰謀論的でイデオロギッシュなものである。
また、『ブルシット・ジョブ』では看護や介護などの「ケア労働」を「エッセンシャル・ワーク」であると定義したうえで、ケア労働者の待遇が悪かったり賃金が低かったりするのも新自由主義だか資本家たちだかの悪どい陰謀のせいである、とされていた。しかし、ケア労働は数ある仕事のなかでも「良いこと」が「良い結果」にかなり直接的に結びやすいタイプの仕事である。つまり、意義ややり甲斐が感じやすくて、バイタル・エンゲージメントが得られやすい職業であるということだ。ケア労働を「天職」であると感じてケア労働に就き続けたいと思う人の数は多いだろう。だからこそ、待遇が悪くなったり賃金が下げられたりしても(ある程度までは)我慢してしまえる人が多い。つまり、ケア労働の待遇の悪さは、新自由主義を持ち出さなくとも、「需要と供給の法則」という経済学の基本的な発想で説明することができるのだ*1。
さて、最後に、ハイトによる「階層間コヒーレンス」に関する議論を紹介しよう。
「コヒーレンス」という単語は一緒にまとまること、くっつくことを意味しているが、たいていは、体系(システム)や思想や世界観の各部分が一貫した効果的なかたちで適合していることを指して用いられる。コヒーレントな物事はうまく機能する。インコヒーレント(コヒーレンでない)な世界観は内なる矛盾によって妨害されるのに対して、コヒーレントな世界観は、ほとんど何でも説明することができる。遺伝学のようなコヒーレントな専門職は、遺伝学のビジネスと歩を揃えて進めていくことができる一方で、ジャーナリズムのようなインコヒーレントな専門職では、自己分析や自己批判に多くの時間を割くことになる。ほとんどの人が、問題があると知りながらも、どうしていいのかについては意見がまとまらない。
多階層でのシステムの分析が可能な時は常に、階層同士が調和して相互にうまく連動する時、特別なコヒーレンスが起こる。性格の分析に、この階層間コヒーレンスを見ることができる。下層である性格が、対処メカニズムとうまく調和し、それがあなたのライフストーリーと一貫している場合、性格はうまく統合されており、日常生活をうまくこなしていくことができる。これらの階層がコヒーレントでないと、内部矛盾とその神経症的な葛藤に引き裂かれたりしがちだ。その調整のためには、逆境が必要なこともある。
(……中略……)
人は別の面でも多階層なシステムと言える。私たちは、物理的なもの(肉体と脳)であり、どういうわけかそこから心が出現する。そして、心から何らかのかたちで、社会や文化が形成される。
(……中略……)
人生が、その人の存在の三層間でコヒーレントである時、人生の意味が感じられるというものである。
(p.326 -327)
この引用部分のあとで、ハイトはコヒーレンスの三階層目にあたる「社会や文化」の具体例として、宗教的な儀式やコミュニティを挙げている。そして、デュルケームによる「アノミー」論的な、「保守的なものとして軽蔑されがちな伝統や社会規範などは、人々の幸福のためには欠かせない」という議論が展開されるのだ。
さて、グレーバーは「クソどうでもいい仕事」の問題を論じたのちに、新自由主義が生じさせる問題を一挙に解決する秘策として「ベーシック・インカム」を持ち出していた。
ベーシック・インカム論に対しては、その実現可能性への疑念や「ベーシック・インカム自体がネオリベラリズム的な発想だ」という批判のほかに、「労働がなくなって社会から切り離された人々は、搾取の対象になったり疎外を味わないとしても、それで本当に幸福になれるのだろうか?」という批判がなされている。この問題意識から、「勤労の権利」や「ジョブ・ギャランティー」という考えが提示されることもある。
実のところわたしはベーシック・インカム論を支持しているので、「ジョブ・ギャランティー」論のパターナリズム性を批判してきた。とはいえ、ベーシック・インカムがアノミーを生み出すということも充分にありえそうな話であるし、仕事や職業を抜きにして「バイタル・エンゲージメント」や「階層間コヒーレンス」を成立させることはおそらくかなり難しいだろうとも思う。実際、失業状態である人々は自殺率が高い、ということも論じられているし。
ということで、仕事は疎外や搾取によって人を不幸にする可能性が高いが、仕事がなかったらなかったで人は幸福から遠ざかる、というのが実情であるように思える。
バイタル・エンゲージメントが得られるような仕事が日本にどれだけ存在するのかって話でもあるし、「気の持ちよう」であることはある程度までは事実であるだろうけれどそれだけでは何ともならない仕事というものも多いだろうし。
わたしが労働や仕事に関する哲学や社会科学の本を積極的に読むようになって2〜3年ほどになるが、どうにも結論は毎回同じようなところに辿り着いてしまうようだ。それはそれとして、グレーバーのような「新自由主義批判者」に対するわたしの敵意だけは、着実に積み重ねられている。仕事という問題に伴う根源的なジレンマや「難しさ」をわざと無視して、仮想敵を作ってそれに対する敵意を煽って「こいつらをやっつければみんな幸せになる」という幻想を人々に振りまいているというのが、偽善者や嘘吐きにしか思えないからだ。それにまんまと扇動されて空虚な「新自由主義批判」を唱え続けている人たちのことも、愚かであるとしか思えないし。
*1:特に日本では、(文系の)アカデミアも、バイタル・エンゲージメントが高いがために需要と供給の法則から待遇や賃金が低劣なものに下げ留められている業界の代表例となっている。海外に比べて日本のアカデミシャンの待遇がとりわけ悪い理由には、もしかしたら「反知性主義」が関わっているのかもしれないし、日本人特有の妬み嫉み根性なんかも関わっているのかもしれない。だが、おそらく、アカデミシャンの賃金や待遇とは放っておいたらどんどん下がるのが「自然」なことであり、それは新自由主義のせいではない。むしろ、他国ではアカデミシャンが放っておかれていないことの方が、「基礎科学の重要性に対する認識」とか「他国に対して科学技術競争に勝利したいという野心」とか「伝統的に醸成されてきた人文学に対する敬意」などなどの理由がなければ起きない事態なのであり、「不自然」なことだと言えるかもしれない。