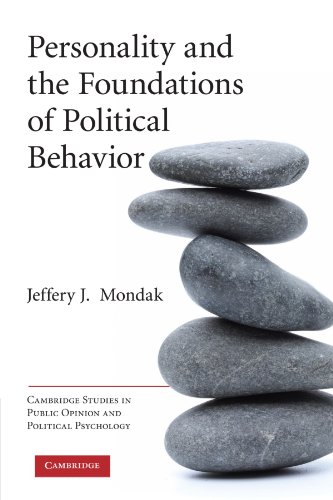『資本主義だけ残った』では、アメリカを代表とする「リベラル能力資本主義」と中国を代表とする「政治資本主義」、現代の社会に存在するふたつの形の資本主義を比較しながら、それぞれの成り立ちや特徴や未来予想図が論じられたりする。
先日に紹介した『自由の命運』や、あるいはフランシス・フクヤマの一連の著作など、英語圏で出版される経済史や文明論では「リベラルで民主主義的な社会は、抑圧的な社会や権威主義的な社会より正しくて望ましい」という規範論が前提とされてしまいがちだ*1。そのために中国のような非民主主義的な国家の経済成長やその他の方面での躍進が予測できなかったり、「一過性のものであって、リベラルな民主主義に移行しない限りは崩壊するに決まっている」と願望込みの予測が述べられたりするようになってしまう。
この『資本主義だけ残った』の最大の特徴は、中国の資本主義をアメリカの資本主義に並び立つものとして論じて、どちらが善くてどちらが悪いかという規範的判断を行わずに、リベラルでも民主主義でもない中国がそれでも資本主義を成り立たせていて経済成長もしていて「うまくいっている」様子を描いて、その理由を分析したところにあるだろう。
政治的目的による資本主義についてのマックス・ヴェーバーの定義は、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』によれば、「経済的利益を得るために政治的な力を使用すること」である。
(……中略……)
今日、政治的資本主義を実践する諸国家、とくに中国、ヴェトナム、マレーシア、シンガポールは、きわめて効率的でテクノクラート的なやり手の官僚にこのシステムを任せることで、このモデルを修正してきた。これはこのシステムの第一に重要な特徴である。すなわち官僚(明らかにこのシステムの主たる受任者)が、高い経済成長を実現し、この目標を達成できるような政策を実行することを主たる義務とすることだ。そしてその支配を納得させるには成長が求められる。官僚が成功するにはテクノクラートであることと、その構成員が成果主義をもとに選ばれることが必要だが、理由は何より法の支配が欠如しているからだ。法の縛りのないことが、このシステムの第二の重要な特徴である。
(p.107)
たとえばフランシス・フクヤマの『政治の起源』や『政治の衰退』では、どんな社会であっても政治が有効に機能するためには「国家」と「法の支配」と「政府の説明責任」のいずれもが成立していて均衡を保っていることが重要である、と論じられていた。そうでない社会は人々にとって魅力がなく、他の社会に対するロールモデルともならない。リベラルな民主主義は自由や尊厳に対して人々が根源的に抱くニーズを充たすから、非民主主義的な社会に暮らす人々も民主主義に憧れて渇望するようになる、というのがフクヤマの主張である。
……しかし、『資本主義だけ残った』によると、「法の支配」はさして重要ではない。政治的資本主義では、テクノクラートなエリートたちには、政治的な目的や私利私欲のために、ときに法を破ったり法を付け加えたりする自由裁量が認められているのだ。当然のごとく汚職や癒着をはじめとする「腐敗」が起こることになり、ときとして役人たちを一斉に調査して摘発する腐敗撲滅運動が行われることもあるが、それはあくまで一時的な対処療法であり、根本的にシステムを変えて腐敗を根絶することは目指されない。
むしろ、中国と同様の状態であったロシアや中央アジアは「法の支配」を導入する試みをおこなったことは、それらの国々にさらに深刻な腐敗をも当たらしたり国内の分裂や内戦をもたらした、と著者は指摘する。中国のほかにも「法の支配」が成り立っておらず腐敗が横行している国は多々あるが、それはそれで効率性や柔軟性があって経済的なメリットがある。「法の支配」は必ずしもすべての社会でプラスに機能するわけではない、と著者は主張するのだ。
とはいえ、法を尊重しない官僚や権力者の横暴が蔓延していて、自分の権利や財産がいつ脅かされるかわからず、当然のごとく民主主義が存在しない社会に、人々が「住みたい」と思えるかどうか、という問題はあるだろう。これについての著者の答えは、「政治的資本主義がうまくいっており、経済成長という"果実"を人々に与える限りは、人々は抑圧や自由のなさもある程度は許容する」といったものだ。
ちょっと長くなるけど、リベラル資本主義と政治的資本主義についてのイデオロギー的な対立に関する議論のコアとなる部分を引用しよう。
……まずリベラル資本主義の利点は、民主主義というその政治システムにある。多くの人(ただし、すべてではないが)が民主主義を「基本善」とみなしているーーそれ自体が好ましいことだから、経済成長や平均余命といったそれがもたらす影響によってあえて正当化するまでもない、と。これはたしかにひとつの利点だ。だがほかにも民主主義には役に立つ強みがある。民主主義ではつねに国民に相談する必要があるので、大衆の福祉に害を及ぼしかねない経済や社会の傾向に対し、強力な是正措置を提供できる。ときに人びとの決断が、経済成長立を下げ、公害を悪化させ、あるいは平均余命を縮める政策をもたらす場合でも、民主主義的な意思決定がさほど時間をかけずにそれらを逆転させるはずだ。有害な発展の抑止に民主主義が役に立たないと考えるなら、過半数の国民が長期にわたってつねに間違った(あるいは不条理な)決断を下していると言わざるをえない。だがそれは見たところ、ありそうにないことだ。
リベラル資本主義のこうした利点に対し、かたや政治的資本主義は、それよりはるかに有効な経済の管理と高い成長率を約束する。これは瑣末な利点ではないし、高い所得や富が最終目標として掲げられる場合はなおさらだ。この価値基準は、まさにグローバル資本主義の発想の根底にあるものだし、そればかりか経済のグローバリゼーションに参加するほぼ全員(実際には地球全体を意味する)の行動にも日々あらわれている。ロールズは、基本財(基本的自由ならびに所得)は辞書的順序を持つと主張した。すなわち、人びとは富や所得よりも基本的自由を絶対的に優先し、したがってその交換は受け入れない。とはいえ日頃の様子を見れば、多くの人が民主主義的な意思決定の一部を所得の伸びと進んで交換したがっているかのようだ。
(……中略……)
所得が上がるのなら、他の民主主義的な権利は放棄できる(そしてそうしてきた)。こうしたことを根拠に、政治的資本主義はその優越性を主張する。
だが問題は、その優越性を証明し、リベラルの挑戦をかわすために(すなわちリベラル資本主義に優先して人びとに選ばれるには)、政治的資本主義はたえず高い成長率を記録しつづけなければならないことだ。よってリベラル資本主義の利点は、それが「自然」なもの、言葉を換えればシステムに組み込まれているものだが、政治的資本主義の利点は、それが役に立つものであることで、たえずその利点を見せつづけることが必要になる。だから政治的資本主義には最初からハンディキャップがある。その優越性を実感させ、証明してみせる必要があるからだ。加えて政治的資本主義には問題がさらに二つある。1 民主主義的な抑制がきかないことから、いったん間違った方向を選んだら進路の切り替えが困難なこと。そして2 法の支配が欠如していることから、腐敗に向かう特有の傾向があること。……
(p.247 - 248)
上記の主張だけを参照したら、リベラル資本主義は政治的資本主義の「自滅」を待っていれば自ずと勝利する、と考えてしまうこともできるかもしれない。たしかに政治的資本主義には経済成長という利点があるかもしれないが、欠点も多数抱えており、経済成長が鈍化してしまった時点で人々は腐敗や抑圧や自由のなさに耐えられなくなって、民主主義とそれに伴うリベラル資本主義を求めるようになるはずだ……と予測することはできる。実際のところ、フクヤマや、『自由の命運』の著者であるアセモグルとロビンソンのおこなっている主張もこんな感じだ。わたし自身も、「"法の支配"は必ずしも不可欠というわけではないんだよ、"法の支配"がなくて腐敗していてもうまくやっている国はあるんだよ」という著者の主張にはイマイチ信用できないところがある。なんか場当たり的というか、現状を後付けで肯定している雰囲気がある。
……とはいえ、それはそれとして、現状のリベラル資本主義は政治的資本主義と比べて相対的に経済成長立が鈍いこと以外にも、深刻な欠点を抱えている。リベラル資本主義は自由で流動性が高いことがウリなはずなのに、実際には不平等を拡大して、格差を固定化させているのだ。
リベラル資本主義が不平等を拡大している要因は様々である。国民所得における労働所得の割合が下がって資本所得の割合が上がったうえに資本が一部の金持ちに集約していること、その一方で現在の富裕層は過去とはちがい資本所得だけでなく労働所得も大量に得ていること(現在の金持ちは有閑階級ではなくバリバリ働くエリートであるということだ)から、所得に対する税金を適切な割合で課することも難しくなっている。
また、女性が高学歴したことにより、学歴や所得の水準が似通った男女が結婚する「同類婚」が増加していることも、不平等の拡大の一因だ。夫婦ともにハイソな家庭に生まれた子どもは資産も文化資本も受け継げる一方で、夫婦ともにそうじゃない家庭の子供はどっちももらえない。さらに、先進国における相続税は、限界税率が下がったり控除の範囲が拡がっていることで弱体化しているのだ。
より深刻なのは、リベラル能力資本主義社会では政党や選挙活動への資金提供が許されているために、政治に対して金持ちたちが発揮できる影響力が増しているということだ。これにより、上位層は自分たちにとって有利な経済政策が実施できるようにコントロールできて、自分たちの立場を永続的なものとできる。
また、大学などにかかる教育費を吊り上げて、よい教育は金持ちしか受けられないようにすることで、知的シグナリングや教育プレミアムを独占できる。それでも、貴族性の社会と違い、ごく一部のきわめて有能な人々は下位層から成り上がって上位層の一員となることはできる。しかしそれも全体から見ればごく僅かな事例であるし、優秀な人間が上位層の一員として取り込まれたうえで「機会の平等は誰にでも与えられている」といったイデオロギーを補強することにもなって、むしろ上位層の地位をさらに盤石なものとするのだ。
要するに、リベラル資本主義でも、政治の正当性は損なわれる。政治的資本主義ではその犯人が官僚であったのが、リベラル資本主義では金持ちが犯人となる、ということだ。その結果として、リベラル資本主義のウリであったはずの「民主主義」や「社会の流動性」といった要素も失われしまうのである。
あるいはリベラル資本主義と政治的資本主義がひとつに収束するのだろうか。
(……中略……)
……リベラル資本主義のもとで経済的な力と政治的な力が結びつけば、リベラル資本主義がますます金権主義的なものになり、政治的資本主義に似通ったものになってくる。後者の資本主義においては、政治的な支配こそが経済的な利益を獲得する道である。もともとはリベラルなものだった金権的な資本主義では、経済力は政治を牛耳るために使われる。この二つのシステムの終着点は同じものになる。エリート層がひとつに結束し、居座りつづけるのだ。
(p.258 - 259)
なんだか黙示録的な結論であるが、著者は、資本所得の集中を少なくして所得の不平等をより減少させて世代間の所得の移動性をより高くした「民衆資本主義」に移行することもできるかもしれない、という可能性についても論じている。そして、民衆資本主義に移行するためには、以下の四種類の政策を実行する必要がある、と主張するのだ。
1・中間層への税制上の優遇措置と富裕層への増税、相続税率の引き上げ
2・公教育への予算の増加と、公教育の質の改善(金持ちの子供が教育面で有利になるのを防ぐ)
3・「軽い市民権」の制度を導入したうえで移民を増やす(著者は、移民は基本的に経済にメリットをもたらす存在であると論じている。ただし、本国人と同じだけの市民権を移民に認めると移民反対運動が起きて移民が入れられくなるから「軽い市民権」を与えるに留めるべきだ、と論じている)
4・政治運動への資金提供の制限
……上記の提言は、「3」を除けば、どこかで聞いたことがあるというか左派やリベラルの人が散々言っているものであり、目新しくはない。そして、これらの政策を実行したくても政治の金権主義化のために困難になっている、というのがそもそもの問題であるのだろう。
リベラル資本主義に関する著者の分析を読んでいてわたしの頭に浮かんだ疑問は、「それって"リベラル資本主義"そのものではなくアメリカという国に特有の問題じゃないの?」ということ。アメリカで公教育の質が悪かったり金持ちから税金を取れなかったりすることは、政治の金権主義化だけでなく、そもそもどんな階層であってもアメリカ人たちがアメリカン・ドリームだかなんだかを盲信して税金や再分配や福祉などを嫌っていることが一因であるだろう。
逆に言うと、アメリカ以外の先進国なら、「民衆資本主義」も実現しやすいんじゃないかという気がする。よく知らないけれど、カナダとか、北欧のどこかとか。というか、すでに存在している福祉国家をロールモデルにすればよいのではないか?
……しかしながら、著者によると、「福祉国家」はグローバリーゼーション時代には破綻する運命にある。福祉国家が機能するためには、国民や労働人口の全員か大半が社会保険に参加する必要がある。しかし、グローバル化した貿易は所得の二極化をもたらし、所得が二極化すると金持ちたちは社会保険ではなく自分たち専用の民間システムを作りたがるし、他の国民のために高い税金を払うことを嫌がるようになる。
さらに、移民の存在も福祉国家にとっては向かい風だ。福祉国家を機能させるためには国民同士の同質性や親近感が必要とされるが、移民はそれを損なう(アメリカで福祉制度が支持されない理由のひとつは、アメリカが多様性の高い…つまり同質性の低い社会であることだ)。また、自分の能力やスキルに自信を持つ移民は不平等な国を好む一方で、自信がなくて悲観的な移民は福祉の発達した国を好む。前者は自分の才覚を活かしてギャンブルをしたくなる一方で、後者は福祉を享受しながらぬくぬくと暮らすことを好むからだ。つまり、競争の激しい国家と福祉国家が並列しているあいだは、「移民の質」という点に関しては、福祉国家はワリを食いつづけるのである。
……などなど。この本における福祉国家に関する議論についても、わたしはイマイチ納得がいっていない。経済学者に特有の福祉国家嫌いを正当化しているだけという疑惑が払拭できないのだ。
では、どのタイプの資本主義もダメなら、いっそ共産主義にすればいいのか?そうはいかない。著者によると、共産主義とは「後進の非植民地国が封建制を廃止して政治的資本主義を築くことを可能にした社会システム」ではあるが、あくまで封建制から資本主義に移行するための足掛かりとしての価値しかなく、持続性のあるシステムではないのだ。
資本主義のほかに、代わりはない。
……この状況は、この社会経済システムが変化を求めているしるしではないのか。もしそうなら、超商業化資本主義社会を捨てて、何か代わりになるシステムに移行すべきではないか。この一見理にかなっていそうな主張の問題点は、超商業化資本主義の代わりになりそうなものが何もないことだ。この世界がすでに試した選択肢はどれもうまくいかなったし、なかにはもっとひどいものもあった。それに何より資本主義に組み込まれた競争的かつ物質欲的精神を捨て去れば、結局は所得が減り、貧困が拡大し、技術進歩が減速ないし逆転し、超商業化資本主義社会がもたらす他の利点(私たちの生活に今や欠かせないモノやサービスなど)を失うことになるだろう。物質欲的精神を捨て、富を成功の唯一の指標にするのをやめても、こうした利点をあいかわらず享受できるなどと思うのは無理な話だ。それらはセットになっているのだから。これはひょっとしたら、人間の条件の重要な特徴のひとつでもあるかもしれない。つまり私たちは、自らの最も不愉快な性質のいくつかを存分に発揮しないかぎり、自らの物質的な生活を向上することができないのだ。これはバーナード・マンデヴィルが300年以上前に探りあてた真実である。
(p.218)
上記の引用文には、「経済学的思考」のエッセンスが濃縮されている。著者の分析や見解には賛成できないものがところどころにあるが、とはいえ、このような「経済学的思考」の鋭さや魅力は否定できない。すくなくとも、わたしたちの気分を良くしたり願望を肯定したりするために根拠のない楽観論や理想主義を無責任に提唱するタイプの議論よりかは、ずっといい。
長くなってしまったから、以下では印象に残ったところを箇条書きで記しておく。
・「あくせく働かずに、余暇を増やそう」的な発想は、人間には「自分の状態を他者と比較する」という性質があるから現実味がない、という理由から否定されている。金をたっぷりと稼いだエリートであっても、周りのエリートたちが稼ぎつづけているうちにリタイアしてしまうと子どもが惨めな目にあってしまうので、自分も稼ぎつづけざるを得ない。そして、グローバル社会では、あくせくと働かずにのんびり生きている人たちばかりの国の土地や不動産は勤勉な外国人に買い占められることになり、そして本国人たちは金を持った外国人たちが贅沢に金を使うのを目の当たりにさせられることになる。
・資本主義社会ではすべての営みに値段が付けられて商品化されるので、家族や地域共同体が担っていた役割もアウトソースされて、社会はどんどん原子化して個人主義化していくだろう、という(よく耳にするような)予測が語られている。また、人々はいままで無償で行っていた自分の活動で金を取れることに気がついて、自由時間も商品化するようになる(ウーバーがその典型)。最終的には「個人」としてのわたしたち全員が資本主義の生産拠点となって、私的領域はすべて商品となる。さらに、富や金が人間の成功や価値の唯一の指標となることで、道徳や行動規範は私利私欲や利己心にとって代わる……などなどといった、月並みなホモ・エコノミクス観に基づくディストピア風未来予測が語られる。
ここらへんの議論にはぜんぜん説得力がない。たしかに富や金だけを指標として生きているっぽい人はいまでもいるがそうでない人もいっぱいいるし、私生活を商品化している人もいればそうでない人もいる、というだけの話にしか思えないのだ(ニューヨークや東京などの都会にこのテのタイプの人が惹きつけられて集まり、各種のサービス売買アプリの技術進歩に伴い都会のディストピア化がどんどん進行する、というのならまだ納得できる)。
・AI悲観論や環境破壊への不安論については、労働・ニーズ・原材料のそれぞれに関する「塊の誤謬」に基づくものである、として否定されている。ここの議論は経済学的思考としても基礎的なものではあるが、直感的な主張の問題点をうまく解体していておもしろい。
・中国に対する評価は全体的に甘くて、「アメリカとちがって中国は諸外国に価値観や倫理観を押し付けず、あくまで経済的な観点からしか貿易や外交をしないだろう」といったことも主張されているのだが、ここはいくらなんでも信用できない。
・先述したとおり、著者は移民の経済的メリットを強調する一方で、移民の権利は制限する必要があることも強く主張する。本国人と全く同じ市民権を移民に求めると、本国人が現時点で市民権から得られている利益が損なわれるし(社会保障や投票権などはそれを得るための資格に制限がかけられていること自体にメリットが存在するからだ)、受け入れを拒否する声が強くなって結果的に移民を入れることが困難になるためである。そして、権利を制限しても移民がやってくるのなら、移民たち本人はあくまで「元の国にとどまるよりもこの国に移ったほうが望ましい」と考えているわけなので、問題はない。とはいえあまりに権利を制限し過ぎたらやってくる移民の数が減ってしまうから、あとは、制限をどれくらいにするかという調整の問題となる。
……この議論も、まさに「経済学」という感じだ。エスノセントリックな移民受け入れ反対論を合理的な観点から論駁している点では、有益でもあるだろう。しかし、技能実習生や入国管理局の問題が日々取り沙汰されている日本に住んでいる身からすれば、「経済的利益や政策的目的のために移民の権利を制限しよう」と堂々と主張する議論は、いかにも危なっかしく思える。もちろん、現時点の世界各国でも移民の権利は多かれ少なかれ制限されているわけではあるのだが、権利について論じるうえでは経済学だけでなく倫理学や政治学の観点が必要になることは明白であるはずだ。