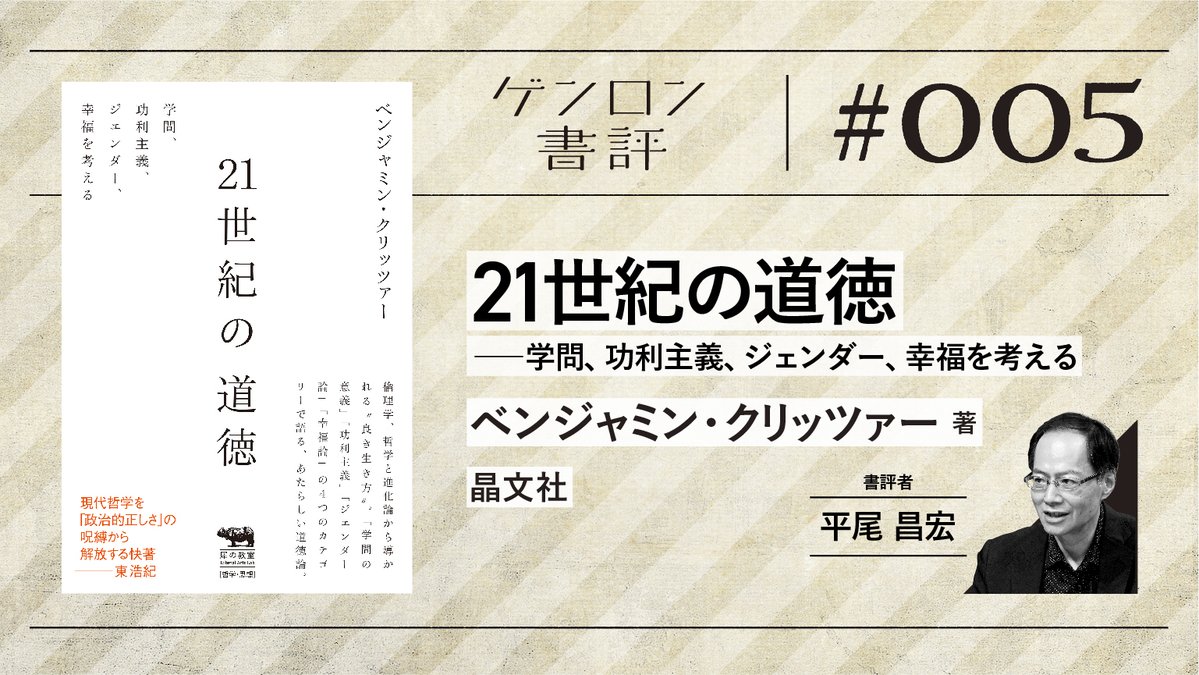とある雑誌に依頼を受けて文章を書き出したはいいものの、批判対象を明示せずにふわっとした印象に基づいてレッテルを貼ってぐちぐち論難する文章になっていき、書き進めているうちに自分でウンザリしちゃったのでボツにして雑誌のほうはまったく異なるトピックや構成でイチから書き直すことにしたんだけれど、それはそれとして、せっかく途中まで書いたのを捨てるのも勿体無いのでこのブログに掲載することにした。
内容としては、とにかくわたしがイラつかされている議論とか風潮とかを一緒くたにしてまとめて非難する、というもの。最近に限らず以前からなんだけれど、本屋に行って『現代思想』とか『文藝』とかを立ち読みするたびにいつもイライラしながら帰ることになっているので、そのあたりのストレスをこの文章に託した。おかげで多少はスッキリしたので明日から書く文章はもっとまともで生産的なものになると思う。
※
人が社会のなかで生きていくうえでは、さまざまな「正しさ」に従わなければいけない。
たとえば、学生であっても働いている人であっても、周りから評価されたり報酬を受け取ったりするためには、課題に取り組む努力をすることや能力を発揮して結果を出すことが求められる。グループワークを行ったりチームとしてタスクに取り組んだりするためには、同級生や同僚とコミュニケーションをとりながら協力しなければいけない。授業や職場に遅刻すると単位や給料に関するペナルティが与えられるおそれがあるから、朝にはきちんと起きて家を出発できるようにしなければならない。いつも体を壊していたり二日酔いでいたりすると勉強も仕事もままならないから、学校や職場の外でも生活習慣に気配りする必要があるだろう。
そして、わたしたちが他人と関わりながら生きていくためには、「感情」を制御することが絶対に不可欠だ。たとえば、授業の内容が気に食わなかったり、他の学生たちがぺちゃくちゃと喋っているせいで教師の声が聞こえなかったり、上司からの叱責が理不尽なものに思えたり、下請けのミスのせいで自分の担当しているプロジェクトに問題が生じたりしたとしても、「怒り」は適切に抑えることが必要とされる。激昂して教師や上司をぶん殴ったり他の学生や下請けの担当者を蹴り飛ばしたりしてしまいたくなる人もいるだろうが、それらの行動を実行すると、学校や職場を辞めさせられるだけでなく警察に逮捕されてしまう可能性もある。机や壁などのモノをどんどんと叩いたり大声を発したりすることでストレスを解消することはできるかもしれないが、それだって人前で行うべきではない。同級生や同僚の目の前でモノに当たっている人は周囲から敬遠されて孤立するだろうし、道端で大声を発すると知らない人にショックや恐怖を与えてしまうことになる。
負の感情だけでなく、親密さや愛情といったポジティブなものにすら、制約をかける必要がある。自分が育てている子供や飼っているペットのことがいくら大好きでずっと一緒にいたいと思っていても、子供やペットを養うためには、家族のなかのだれかは家の外に出て働きにいかなければならない(自宅でリモートワークするにしてもずっと子供やペットを相手にしていられるわけではないだろう)。ゼミや職場にいる誰かのことを恋愛的な意味で好きになってしまったとしても、その好意を示すことには慎重になったほうがいい。相手から受け入れられなかったり嫌がられたりすると、お互いにとって、学校や会社に行くことが負担になってしまい、社会生活に影響が生じてしまうからだ。誰かと一緒になるためには、相手の意思を尊重しながら、段階を経て仲良くなっていく必要がある。一緒になった後も、二人の生活を維持していくためにはやはり社会に出て金を稼ぐ必要はあるだろうし、相手からの好意を維持するために気配りも必要となる。
要するに、「正しさ」とはわたしたちに不自由を押し付けるものである。現代社会に暮らすわたしたちは、所属する集団や身の回りの人たち、あるいは道ですれ違う知らない人たちや顔を合わせることもない人たちを含む「世間」のことも考慮しながら、自らの行動や習慣や感情を制御する必要がある。そうでなければ法律によって懲罰を受けたりするかもしれないし、学校を卒業してやりたい職業に就いたり会社で出世して給料を上げて欲しいものを買ったりするといった自分の望みを実現することもできなくなる。つまり、現代社会では「正しさ」に従っても従わなくても、結局は不自由になってしまう。「正しさ」から逃れることはできない。
とはいえ、みんなが「正しさ」に従っているからこそ、社会は安全で豊かな場所になっている。
自分が街を歩いているときのことを考えてみよう。街中でなにかムカついたことがあるときに大声を発せないのは、たしかに不自由であるかもしれない。けれども、街を歩いているときに大声を発する人と遭遇することは、たまにはあるかもしれないが、すれ違う人の数を考慮するときわめて稀である。みんなが些細なきっかけで生じる怒りやムカつきをその場で行動に表出するような街はおそろしく物騒で緊張に充ちた環境になり、誰も住みたいと思わないはずだ。それに比べると、自分を含めたみんなが怒りやムカつきを抑えることのほうが、多少不自由であってもずっとマシである。ほとんどの人はそう考えるはずだ。
そして、街を歩いていれば、見知らぬ誰かが「正しさ」に従っていることの恩恵をさまざまなかたちで得ることができる。ゴミの日でもゴミ袋が昼まで放置されていることはない。ゴミ収集業者の人たちが朝のうちに回収してくれているからだ。自販機はたまに飲み物を切らしていることもあるが、大体の場合は好きな飲み物を選んで買える。業者の人が補充してくれるから。コンビニでは常に誰かが働いているから、空腹になったら24時間のうちのいつでも入ってなにか軽食を買うことができる。ついでに言うと、その食事の原材料は国内か国外の農家の人たちが働くことによって生産されたものだろう。ゴミ収集にせよ農業にせよ、それらの仕事をしている人は一般的な会社員よりも早起きしており、そのために生活習慣を律している。飲料を補充する業者の人やコンビニ店員が規律を守らずに好き勝手に動いていると、喉が渇いたりお腹が空いたりしても飲み物や食べ物を得られなくなってしまうかもしれない。もしある日突然そんな状況になってしまったら、わたしたちの生活は台無しになるだろう。「ゴミ収集業者の人もコンビニの人も仕事をしなくなる代わりに、あなたも仕事をしなくて良くなるよ」と言われたとしても、ほとんどの人には受け入れ難いはずだ。わたしたちの生活は、習慣を整えて規則を守りながら自分の持ち場で仕事をするという「正しさ」に自分も他人も従うことで、そうでないよりもずっと便利なものになっている。
わたしたちの生活に彩りや充実を与えるエンターテイメントすら、「正しさ」を前提としていることも忘れるべきではない。マンガや映画やドラマでは多種多様な物事が展開されており、そのなかには、わたしたちが縛られているような「正しさ」が存在しないファンタジー世界を舞台としたものもある。けれども、マンガ家が締め切りを守って編集者がそれを確認して印刷所やWeb会社の人などが働かなければ、わたしたちはそのマンガを手に取ったりスマホに表示したりして読むことができない。そして、映画やドラマの制作現場と流通に関わる関係者の数はマンガの比ではない。その人たちのすべてが、時間や規律を守りながら自分の職務をこなすことでようやく、わたしたちが楽しむ物語が生産される。このことは、音楽やスポーツ観戦などのほかのどんなエンターテイメントについても多かれ少なかれ当てはまるはずだ。
ここまでにわたしが書いてきたことはきわめて凡庸で、当たり前のことだ。社会の構成員のみんながルールを守り、行動や感情をコントロールして、自分の勤めを果たす。そうしない人の数が増えると社会の安全や豊かさが失われてしまうから、みんなが「正しさ」を守るべきであり、守らない人にはなんらかのペナルティを与えるべきだ。
凡庸で当たり前のことであるとはいえ、この考え方は、古代から道徳や政治に関する哲学の基本的な発想となっている。古代ギリシャなどで語られていた「正義」にせよ、古代中国などで語られていた「徳」にせよ、社会秩序という観点を抜きにしては論じられていなかったはずだ。近代になってからは、「みんなが秩序を守ろうとしないと全体的な環境がより悪くなってしまうから、秩序を守らない人に制裁が科されることを認めたうえで、自分も秩序を守ることに同意する」という理路で「正しさ」の起源や必要性を論じる主張が、「社会契約論」というかたちで発展してきた(社会契約論にもいろいろあるけれどここではホッブズのそれを特に想定している)。同じく近代になって本格的に登場した経済学では、「正しさ」が豊かさをもたらすということが、現在に至るまで論じ続けられている。
もちろん、道徳や政治に関する哲学にせよ、経済学にせよ、各時代の社会における「正しさ」をそっくりそのまま認めてきたわけではない。たとえば、君主や貴族が過剰に権力を握っており、自分たち以外の人たちに比べて不当に多くの豊かさを得ていることや、他人たちに必要以上の不自由を押し付ける一方で自分たちは守るべきルールから逃れられていることが、平等や正義の理念に反しているとして批判されてきた。現代であっても、資本家や富裕層が社会に対して然るべき貢献もしていないのに過度な富を得ていること、規則を守りながら大変な仕事をしている労働者たちが得られている報酬が労力にまったく見合っていないことなどが、「搾取」であるとして批判されている。とはいえ、それらの批判は、「正しさ」を否定するものではまったくない。そこで目指されているのは、その時々における秩序が歪んでおり貴族や資本家などにとって都合の良いものになっていることを指摘したうえで、本来あるべき「正しさ」を実現しようとすることだ。
だから、倫理学や政治哲学における主流派の見解は、現状の世間における「正しさ」を一概に否定しないものであることが多い。「正しさ」の範囲を広げて、わたしたちに課される要求や義務を足すことはある。たとえば、わたしたちは自分の住んでいる地域や国内の人だけでなく海外の人についても配慮するべきだと要求したり、人間に対する義務だけでなく動物に対する義務もわたしたちは持っているのだと論じられたりする。しかし、わたしたちに課せられている要求や義務が減らされるべきだという主張は、なかなかされない。現状の「正しさ」においてわたしたちが他人に配慮しなければならなかったり自分を律したりしなければならないことは適切であるとしたうえで、それでもまだ理想の「正しさ」の基準に到達していない、と論じられる。そして、制度を変えたり資本家や政治家などの特定の層が負うべき義務を増やしたりするだけでなく、個々の一般人であるわたしたちの行動や生活スタイルまで見直す必要がある、と主張されるのだ。
したがって、倫理学や政治哲学、あるいは経済学や公共哲学などでなされる「正しさ」に関する議論の大半は、わたしたちにとっては鬱陶しく面倒で不愉快なものだ。現状の社会は(20世紀以前などに比べれば)それなりに豊かであるとしても、多くの人にとって賃金は未だ少なく労働時間は長い。「搾取されている」と客観的に判断されるような人や、ワーキングプアであったりする状態の人に関しては、賃金を上げたり補助がされたりするべきだということは「正しさ」の論理でも主張されるが、それとは別問題として、経済状況がどうであれどんな人も規則を守ったり義務を負ったりするべきだとも論じられる。現時点でつらい気持ちを抱いている人にとっては、自分のすべきことについていま以上にこと細かく要求したり新たな種類の義務を負わせたりしようとする倫理学的・政治哲学な「正しさ」は理不尽でイヤなものとしか感じられないだろう。だが、主観的な「つらさ」は「正しさ」から逃れる理由としては認められない。このため、大半の人にとって、「正しさ」の論理から救いを得られることはできない。
それに、なんといっても、「正しさ」に関する議論はつまらない。ある意味、倫理学や政治哲学の本の大半とは、大人向けにレベルアップした「道徳」や「公民」の教科書でしかない。それは読んだり聞いたりしていてワクワクするようなものではないのだ。
このため、大半の人が本を読むときには、「正しさ」に関する議論とは異なるものを期待する。
最も手っ取り早いのはフィクションだろう。『実践の倫理』や『正義論』などとは違い、『呪術廻戦』や『ゴールデンカムイ』は読んでいて気晴らしになる。疲れたり集中力がなかったりするときでも読むことができるし、読んだらストレス解消になる。このあたりが、本を読む人の多くがマンガだけしか読まなかったり、活字を読む場合にも小説しか読まなかったりする理由だ。なにが正しいのかとか、世の中はどうあるべきだとか、わたしたちはどう生きるべきかとかいったことに関する議論について、ふつうの人は学校を卒業した後にも自分から本を手に取ってまでして付き合おうとはしないものなのだ。
とはいえ、世の中には、小説以外の活字本も開いてみて、社会や政治や道徳といった事柄に関する議論に触れてみようとする人もいる(忘れられがちだが、この時点で、その人はそれなりに奇特である)。だが、社会や政治や道徳に関する本を読む人であっても、「正しさ」を求めているとは限らない。大学などで研究している人ならいざ知らず、そうでない人たちが政治や道徳に関する議論に求めるものとは、「優しさ」であることが多いようだ。彼や彼女は、規律を守ったり感情を制限したりするといった「正しさ」を否定して、自分が社会に適応させづらい資質を持つことや社会の秩序についていけないことを受け入れて、自分が抱いている感情をありのままに認めてくれるような議論を期待しているのである。
「正しさ」を否定する「優しい」議論にも、いくつかの種類がある。
わかりやすいものとしては、「すべての道徳や規範は虚偽であり無意味であるので、わたしたちがそれらに従う義務や必要は一切ない」といった、ニヒリズムやアモラリズム(無道徳主義)を唱えるものがあるだろう。この主張を敷衍すれば、他人を不愉快にさせないために感情を抑えたり身近な人に迷惑をかけないために遅刻しないようにしたりするといった「正しさ」も、作り事であるとして否定することができる。
……とはいえ、ニヒリズムを認めると、自分だけでなく他人までもが「正しさ」を守らなくてよいということになる。そうすると、友人や同僚に遅刻されて迷惑を被ることも受け入れなければならなくなるし、いつ自分が他人の怒りの捌け口とされて殴られてしまうかもわからなくなってしまう。
結局のところ、ニヒリズムやアモラリズムは「力ある強者が自分の意思を押し付けて、力のない弱者はそれを粛々と受け入れる」といった弱肉強食的な世界や「お互いの利益になっている間は相手と協力したり約束を守りあったりするけれど、利益にならなくなった途端に協力を打ち切って約束を破る」といった殺伐とした世界を肯定することにしかならない。それでは、「優しさ」を期待する人たちが求めるのとは正反対の議論となってしまう。
このため、「優しい」議論の多くは「正しさ」のすべてを否定しようとするわけではない。実際には、ある種類の規則に従ったり義務を守ったりする必要があることは認めながらも、別の種類の規則や義務の必要性を却下することで、自分にとって負担となったり都合が良くなかったり気分が悪かったりする「正しさ」だけを部分的に否定する議論が主となっているのだ。
現行の「正しさ」を否定する議論のなかでも代表的なものが、旧来の議論の前提となっている人間像を批判するタイプのものだ。
たとえば、昔ながらの社会契約論では人間が利己的な存在であるとみなされて、自然状態では互いを利用しあって傷付けあう存在だと考えられるからこそ、国家や制度による強制や制裁が必要であると主張される。
これに対して、「優しい」議論では、「人間が利己的な存在である」という前提が否定される。つまり、国家や制度がなくとも人間は互いを尊重しあうことができ、生産的な協力を実現したりすることもできる、と論じられるのだ。
この議論によると、政治哲学は過剰に利己的な人間像を描いてきたために、国家によってわたしたちの自由が不当に制限されたり、私人たちが信頼に基づく豊かな人間関係を築く機会が諸々の制度によって奪われたりすることを看過してきたと主張される。本来、国家にあれこれと行動を制限されたり指図されたりしなくても、わたしたちは平和で安全な社会を自発的に築けるはずだったかもしれない。むしろ、殺伐とした人間像に基づく政治システムの下で暮らすことによって、私たちは味気なくストレスフルな「正しさ」に従属させられる羽目になっている……と主張されるのだ。
また、政治哲学とセットで経済学が槍玉に挙げられることも多い。経済学は人間が合理的に利益を追求する存在であると前提したうえで自由市場や資本主義などのシステムを肯定してきただけでなく、それに伴うさまざまな弊害にも目を瞑ってきた。現行の社会で搾取や格差が激しくなっていて、再生産労働が軽視されていて、地球温暖化や環境破壊が深刻化しているのは、すべて経済学が合理的な人間像を前提にしてきたせいだと、「優しい」議論は主張する。
だが、もし人間は経済学が前提としているほど合理的な存在でなく、利益を追求するだけでなく他者への愛情や信頼などを重視できる存在であるとしたら、自由市場や資本主義などとは異なるかたちの経済が実現できるかもしれない。そのような経済に基づく社会では、現行の「正しさ」に従わなくても、わたしたちは豊かに過ごせるはずだ。新しい経済は貨幣ではなく贈与に基づいたものになるかもしれないし、生産手段は独占されるのはなく共有されるかもしれない。すくなくとも株式とか資本といったものはなくなりそうだし、格差や搾取もなくなりそうなものだ(それらは自由市場や資本主義に特有のものとされるから)。現行の社会では多くの人が生きるためにしたくもない仕事をしているが、新しい経済の下では、みんなが自分の価値観に基づいてやりたい仕事をできるようになるかもしれない。もしかしたら24時間営業のコンビニや自販機といった便利なものもなくなるかもしれないが、農業やゴミ収集といった社会に不可欠な仕事は存在しつづけるだろう(人間は愛情や信頼を大切にできる存在であるとすれば、だれかがやらなければみんなが困るような仕事は、どこかのだれかが自発的にやってくれるはずである)。
もちろん、そのような社会では、資本主義における「正しさ」の多くに従わなくてよくなるはずである。たとえば、現行の社会では「お金を必要としているなら、(そして仕事ができるような状態であれば)職を探して働き始めなければならない」「もっとお金を稼いで豊かになりたいなら、職場で能力を発揮したり資格を取ったりするなどの努力をしなければならない」といったことが常識となっており、それによって仕事が嫌いであったり苦手であったりする多くの人が苦しめられているが、経済が資本主義でなくなるならこの常識からも解放されることが期待できる。
政治や経済に関する「優しい」議論を素描すると、上述したようなものになる。
言うまでもなくこの素描は戯画的であり誇張したものではあるが、ポイントをまとめると以下のようになる。
「優しい」議論では、主流派の政治学や経済学の議論が前提とする利己的で合理的な人間観を否定することによって、現在の社会の主流となっている「正しさ」も否定する。そして、利己的でも合理的でもない真の人間像を発見することとで新たな「正しさ」を想像することができる、という示唆がなされる。
…とはいえ、それは示唆に留まることがほとんどであり、現在の国家制度や資本主義システムの代替になるような具体的な展望が示されることはほとんどない。せいぜいのところ、過去のどこかや現在の辺境に存在している一部の部族社会や農村社会について、安全でないとか不便であるとか貧しいとかいったことには目を瞑りながら理想化するだけだ。それらの社会が現在の社会のオルタナティブになると本気で主張するわけではなく、どちらかというと、国家や資本主義に伴う鬱陶しくて窮屈な「正しさ」の束縛から解放されるという「夢」を託すかのような議論が多い。
そして、それこそが「優しい」議論を求める読者が望むものである。結局のところ、自分の暮らしている社会の前提となっている国家や資本主義といった制度がなくなったり大幅に変わったりするという主張にリアリティを感じるのは難しい。変わるとしても自分が生きている間に変わるかどうかはわからないし、変わったとしてその社会が現在より良くなるかどうかについても確信は持てない。だから、現行の「正しさ」を否定しつつ、そのオルタナティブは「夢」として、曖昧で手の届かないものとして描かれるくらいがちょうどよいのだ。
とはいえ、政治学における社会契約そのものは「正しい制度や政治とはなにか」を問うための仮説であったり思考装置であったりするとしても、「人間が利己的な存在である」という前提は、通常、説得力を持つものと見なされてきた。
国家などの強制力がなければ人間が他人に対してどこまで残忍になれるか、規律を守らずに好き勝手して社会がどれほど混乱するかということは、歴史上や現時点に存在する数々の事例を見ればわかる。
また、「人間は合理的な存在である」という前提については、経済学のなかでも数々の修正が加えられている(いまでは人間の「不合理性」を強調する行動経済学の議論を知らない人はほとんどいないだろう)。しかし、「人間はある程度の不合理さを持つ存在である」ということが正しくても、「人間はまったく不合理な存在である」ということにはならない。そして、人間に利他心や不合理さが多少ばかり存在するとしても、現行の国家制度や資本主義システムはそれを織り込んで依然と存在することはできる。結局のところ、オルタナティブな「人間像」を描くことで既存の「正しさ」を否定しようとする議論はうまくいかないのだ。
「正しさ」を否定する「優しい」議論には、ほかにもさまざまなタイプがある。
飽きてきたのでここからはさらに雑な紹介になるが、たとえば、健康や公衆衛生に関わる諸々の政策などを否定する議論。現在の社会では自分の健康を守るために(そして健康を崩して他人や社会に無用な迷惑や負担をかけないために)食生活や生活習慣を律することが期待されていて、タバコの副流煙は他人の健康を侵害するものであるから喫煙場所が制限されていて、ワクチンの接種は自治体や職場から半ば強制されていてと、健康に関する諸々の行動が「正しさ」によって制限されたり押し付けられたりする。だが、自分の健康を顧みず暴飲暴食したい人や他人の迷惑も気にせずにタバコを吸いたい人やワクチンが不安で接種したくない人は、そういう「正しさ」をもちろん嫌がる。そんな人たちのためには、生権力がどうこう言ったり管理や支配があーだこーだと言ったりしながら健康や公衆衛生に関する「正しさ」を否定する「優しい」議論が存在している。
生活したり他人と協働していくためには感情を適度に抑えて、人に対して意見を言ったり要求したりするときにはできるだけ冷静で客観的であったほうが望ましい、という「感情」に関する「正しさ」についても、それを否定する「優しい」議論は存在する。とはいえ、中年男性がキレることまでをも肯定する議論は存在せず、基本的には女性やその他のマイノリティだけの感情を選択的に肯定する議論となる。たとえば、「“女性は感情的で非理性的な存在である”というステレオタイプが存在してきたからこそ、女性は自分の感情を抑えようとするプレッシャーにさらされ続けてきたし、女性の発言はどれだけ冷静で理知的なものであったとしても耳を傾けられてこなかった」といったジェンダーに関する「歴史」が滔々と述べられたうえで、「女性はどうせなに言っても感情的だと言われるんだから、それじゃあむしろこれまで抑えつけてきた感情を表出することのほうが正しいのだ」といったロジックによって、女性の感情を怒りといったネガティブなものも含めてまるごと肯定する……といった議論がここ最近ではかなり流行っている。
健康に関するものにせよ感情に関するものにせよ、これらの「優しい」議論には普遍性がないことが難点だ。暴飲暴食する人や所構わずタバコを吸う人やワクチンを拒否する人が少数派であるうちは問題ないが、多数派になると社会の負担が過大になって保険制度に歪みが生じたり公共空間が機能しなくなったりする。男性の「怒り」までもが肯定されるようになるとどう考えても世の中がロクでもないことになるのでジェンダーの「歴史」についての主張を経由して女性の「怒り」だけを選択的に肯定するわけだが、その「歴史」にどこまで信憑性があるかわからないし、歴史がどうであるかということと現在の社会のなかで生きている女性がどうするべきかということは本来別問題であるはずだ。
結局のところ、「正しい」議論とは異なり、「優しい」議論は、それに触れる読者の感情や願望を肯定するためのものに過ぎない。
政治や社会について論じてはいるが、自分たちの結論が社会的に採用されて政策などに反映されたり一般の人たちの価値観を変えたりするとは、「優しい」議論を行なっている当人たちも思っていないし、それを志向すらしていないかもしれない。その議論は学会や論文誌や学術書や文芸誌や素人のブログやSNSの駄弁りなどのなかで完結するものに過ぎず、現状の「正しさ」をイヤに思っていたり負担に感じていたりする人の気持ちを一時的に解放して「世の中がこんな風であったらいいのになあ」という幻想に浸らせる、気休めであるに過ぎないのだ。
とはいえ、漫画や映画といったエンターテイメントが気休めであることは周知の事実であるのに対して、「優しい」議論の提唱者たちは自分たちがやっていることが気休めであることを公言しない。「優しい」議論が読者たちに見させる夢のリアリティを増すためには、「正しい」議論に並び立って反論を行なったりする「議論」の形式をとりながらもっともらしさをキープすることが重要なのであり、「わたしたちのやっていることは議論ではなく気休めなんですよ」と公言した時点で、気休めとしての効果が失われてしまう。
そのために、「優しい」議論を本気で真に受けてそれに一生を捧げてしまう人もいるし、才能や知能を持つ個人や税金とかの公的なリソースが「優しい」議論に吸収されてしまう。それらの個人やリソースが「正しい」議論のほうに投入されていたら、世の中はもっとよくなっていたかもしれない。
まじめに物事を考えたいときには「正しい」議論に付き合うべきである。そうでなく気休めが欲しいときには難しい本ではなく漫画を読めばいいし、Netflixを観たりゲームしたりしていればよいというのが、わたしの言いたいことだ。