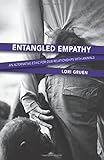
Entangled Empathy: An Alternative Ethic for Our Relationships with Animals by Lori Gruen(2014-01-01)
- 作者:Lori Gruen
- 出版社/メーカー: Lantern Books
- 発売日: 1739
- メディア: ペーパーバック
離職して、しばらくの間は本を読む時間もたっぷりとある。2年以上前にフルタイムでの仕事を始めてからは洋書を読む習慣が失われていたので、それを取り戻すためにも、手始めにページ数の少ないこの本を手に取った(約100ページほどだ)。
この本は、『動物倫理入門』の著者でもありエコロカジル・フェミニストでもあるローリー・グルーエンが、動物の問題に留まらない諸々の倫理問題に向き合ううえでの自身の倫理学的考え方をまとめたもの。『動物倫理入門』のなかでもグルーエン自身の立場が紹介されていたが、それをより詳細に展開されているような感じだ。
グルーエン自身の立場は、エコロジカル・フェミニズムに基づくものである。本書のなかでも「倫理は感情ではなく理性に基づくものである」「自律した他者を尊重することが道徳的配慮である」といった考えを否定して、「理性ではなく、他者に対する共感やケアの感情こそが道徳の源である」「自律を強調するのではなく、他者との関係性や依存性を尊重することこそが道徳的配慮である」といった、フェミニズム倫理・ケアの倫理の考えがところどころで紹介されている。
しかし、グルーエンの主張には、ケアの倫理やフェミニズム倫理につきものの弱点が相変わらずつきまとう。これらの弱点については以前の記事でも指摘しているが、簡潔にまとめてみると「感情や"共感"を理想化し過ぎていてそれらの問題点や限界を軽視してしまっている」ということと、「一貫性のない場当たり的な理論であるために、複雑な事例やトレードオフが発生する事例などでは行為の指針にならない」ということだ。
この本では『反共感論』を著しているポール・ブルームや『はらわたが煮えくりかえる』の著者のジェシー・プリンツによる共感に対する批判的な意見を受けつつ、「共感」という行為はブルームやプリンツが論じているように浅はかで恣意的な生理的感情には還元できない、複雑で繊細な倫理的営みである、という風に論じることで「共感」を擁護し、共感に伴うとされがちな問題点や限界を乗り越えようとする。そのために、グルーエンは望ましい「共感」の方法について詳細に論じるし、間違った仕方での共感と正しい仕方での共感との区別も行う。簡単に言ってしまうと、共感の対象となる相手に固有の事情や性質、その場の状況における特徴などについて注意深く認識して理解しようと努めて、自分の尺度や価値観だけで考えるのではなく相手に立場に立って考えるように努めることで、適切な倫理的判断ができるようになる、といった感じだ。…しかし、相手やその状況の事情を「理解」しようとすることや「相手の立場に立って考える」ことはそもそもが理性的な営みであるし、まさにケアの倫理が批判の対象とするところの各種のオーソドックスな倫理学理論こそが、それらの営みを行うべきであるという主張を行なっているのだ(たとえば、R・M・ヘアの功利主義は「相手の立場に立つ」という営みを追求した結果として導かれるものである、といえる)。
これは「ケアの倫理」や「フェミニズム倫理」が主張される場合にありがちな問題である。まず、権利論や功利主義などのオーソドックスな倫理学理論を「理性を重視し過ぎていて感情を軽視している」と批判する。そして、感情を重視するケア倫理やフェミニズム倫理を主張する。だが、感情を重視することに対しては様々な問題が指摘される。そのため、「ケア」や「共感」という単語の定義を拡大したり注釈や条件を加えることによって批判に対して応答しようとする。しかし、定義が変えられた後の「ケア」や「共感」は、当初のそれらの言葉が意味していたようには感情を重視せずに、理性を重視する側面が強まってしまう。つまり、結局は当初に批判していたオーソドックスな倫理学理論の問題点を自分たちの理論にも輸入してしまうことになるのだ。…これは「ケアの倫理」に限らず、オーソドックスな倫理学理論の理性重視や理論重視を批判するタイプの倫理学的主張のいずれにも起こりがちな構造であるように思える(徳倫理や状況主義、個別主義など)。
ただし、理論としては構造的問題点を抱えているケアの倫理ではあるが、細部には見るべきところや面白いところもある。たとえば、この本では、身近な対象に"共感"を抱くという経験が、身近ではないその他の対象へと"共感"を拡大させることにつながる、という議論が行われている。たとえば、動物愛護運動に参加する人や動物の権利運動に参加する人の多くは自らがペットを飼っており、そのペットを飼う経験を通じることで「動物好き」(animal person)となり、自分のペット以外のコンパニオンアニマルや家畜や野生動物にも共感を抱くようになって彼らの状況を改善するための運動に身を投じるようになる、という経歴の人が多い…ということが指摘されているのだ。また、動物の問題に向き合う経験は人種差別や性差別やグローバルな貧困などの他の問題にも関心を抱かせる窓口となることが多いし、逆もまた然りである。
たしかに、私自身も動物の問題に関心を抱くきっかけになったのは実家で猫を飼っていることにある。オーソドックスな倫理学理論だとペット飼育に関わる問題点ばかりが指摘しがちであって、「ペット飼育の経験が動物倫理の問題全般に対しての関心を広げる」という事象について論じることが難しい。このような事象について論じるうえでは「ケアの倫理」に軍杯が上がると言えるかもしれない*1。
おそらく、「ケアの倫理」は行為の指針としての倫理学理論としては不適切であるし、無理に理論化しようとしたり精緻化しようとすると苦しいものになる。それよりも、様々な複雑な問題や特殊な事象について倫理学的に考えるときの引き出しのひとつとして保持しておく、くらいの使い方がよいのかもしれない。
*1:ただし、ピーター・シンガーやスティーブン・ピンカーが「黄金律」「話の拡大」について論じていることやマイケル・シャーマーによる「道徳的フリン効果」の議論も「共感対象の拡大」という事象については論じており、グルーエンの議論ともニアミスしているように思える。