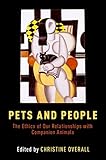経済学の祖であるアダム・スミスの主著といえば『国富論』だが、この本ではもう一つの代表作である『道徳感情論』の中身をわかりやすく解説して、現代の世界における我々の生活に『道徳感情論』の知見はどう関係するかということも論じられている。
基本的に紹介する内容を『道徳感情論』のみに絞っているので話があちこちに飛ぶこともなく、また現代社会における諸々の事例を挙げながら解説してくれるので、『道徳感情論』で述べられている知見の面白さや意義なんかも伝わりやすい。一人の思想家に絞った哲学の入門書は幾多も出版されているが、その中でもかなりクオリティが高い方だと思う*1
・第8章「世界をよりよいするところには」では、道徳規範の発生の起源について論じられている。著者は、道徳規範の発生を言葉の発生になぞらえて論じている。現代の社会でも気が付いたら新語が発生して定着することがあるが(「ググる」など)、それはどこかの権力者や組織などが「この単語を新語として認定する」と言って決められるものではなく、人々が自然とその単語を使っていきその単語の意味もなんとなく理解されることで定着していくものである。そして、道徳の決まり方も言葉の決まり方と同様である、と著者は(アダム・スミスの口を借りて)説く。
私たち一人ひとりの行動は、積もり積もって道徳規範や信頼関係を、ひいては市民社会を形成するけれども、誰ひとりとしてそのような結果を望んでいるわけではない、と先生は見抜いていた。それどころか、そうした結果は自然にもたらされる。誰も、自分の行動で社会がよくなるとか社会を変えられるとは思っていない。思っていないけれども、結果的にそうなる。
(p.210)
世界をよりよいところにする方法は、たくさんある。ノーベル平和賞の対象になるような非営利組織を設立するのもいいだろう。政治家になるのも、一つの方法だ。だが、私たち一人ひとりの小さな行為にも大きな意味があるのだとスミス先生は語っている。そうした行為に派手さはないが、大勢がひっそりと行う行為が積み重なれば、信頼と尊敬の文化という大きな成果につながる。
(p.229)
世界をよりよいところにしたいなら、信頼される人になり、信頼できる人を大切にすることだ。よき友になり、良き友を大切にすることだ。他人の悪口は言わず、他人を貶めるジョークには笑わないことだ。そうした小さな一つひとつのふるまいが、自分の手の届かないところにいる人にもそうしたふるまいを促すことになる。よき人であることは、かくも大きな影響力があるのだ。
(p.230)
余談だが、『殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか?』という本では、スミスが『国富論』で述べたような「分業」と「交換」による経済の発展の前提には、初対面の人間同士でも経済行為が成立するための信頼が発展する必要があった、ということが論じられていた。この本とつきあわせて読んでみると面白いかもしれない。
・スミスは、幸福になるためには「愛される人になる」ことが最も重要だと論じたそうだ。他人との関係や他人からの評価が自分の幸福に直結するという考え方は、現代的な観点から言ってもなかなかリアリティがあって的を得ているように思われる。また幸福とは愛される人になることだ、という考え方は「なぜ道徳的にならなければならないか?(Why be moral ?)」問題への答えにも直結する。幸福になりたいなら、人から愛されるような道徳的な人間にならなければならない、ということだからだ。
・愛されること、に並んでこの本で強調されるのが「中立な観察者」というキーワードだ。この単語はスミスが『道徳感情論』で行った議論の中核になるものとして有名で、独立したWikipedia記事にもなっていたりする*2。また、第4章の「自分をだまさずに生きるには」では自己欺瞞が取り上げられている。自己欺瞞というテーマは現代の心理学や行動げ経済学でもよく注目されて面白い研究結果が色々と出ているテーマである。
・第7章の「よき人になるには」では、他人から愛されるような「徳」を備えた人とはどんな人であるか、ということが論じられる。スミスは「思慮」「正義」「善行」を三大徳と見なしていたらしい。そして、思慮のある人とは、慎重で考えなしな行動をしない人であり、そして、謙虚な人である。以下の引用文がスミスの考える「思慮深い人」の具体例であるが、これを読むと、大言壮語ばかりで中身の伴わないベンチャービジネスが華やかしく、自分を誇示することしか能のないインフルエンサーたちが憧れの的になる現代で「思慮深い人」を讃えることはなかなか時代に逆行している感もある。
思慮深い人は、巧妙な詐欺師のように悪知恵を働かせたり、学者きどりで傲慢な態度をとったり、底の浅いあつかましい偽善者のもっともらしい口上で人を欺いたりはしない。実際に持っている能力でさえ、けっして誇示しない。世間の注目を集め名声を得ようとして人々が用いるあやしげな手口はことごとく嫌い、飾り気なく謙虚に語る。
(p.173)
・第1章で出てきた、気の利いた文章。
人生から最も多くを得るとは、賢い選択をするということだ。そして選択をするときには、この道を選んだらあの道は選べないとわきまえ、自分の選択は他人の選択に影響をおよぼし、他人の選択は自分の選択に影響をおよぼすと知っていなければならない。これこそ、経済学のエッセンスである。
(p.21)
・第5章「愛されるには」では、以下のような文章が出てくる。
テクノロジーを巡るスミス先生のすぐれて現代的な指摘の一つは、人々が高度な機能にこだわる割には、その機能を実際に役立てていないことである。
(略)
“時計に凝る人が必ずしも他の人より時間に几帳面だとは限らない。また、何か別の理由からいまが何時何分かを熱心に知りたがるわけでもないだろう。この人にとって関心があるのは、時刻を知ることよりも、時刻を知らせる機械が完璧であることなのだ。”
そして先生は、あたらし物好きにぴしゃりと一撃を喰らわせる。
“たいして役に立たないつまらないものに無駄金を投じ、財産を減らす人がどれほど大勢いることだろう。この手の玩具に目がない人にとっては、効用そのものより、効用を増やすようにできていることがうれしいのだ。そして、役立たずの小道具をポケットに詰め込み、さらにふつうの服にはついていないような新種のポケットまで工夫して、もっとたくさんの品物を持ち歩こうとする。”
いやはや、「役立たずの小道具をポケットに詰め込む」とは、言い得て妙である。…
(p.108-109)
これに続く文章では、著者は現代社会の"たいして役に立たないつまらないもの"の象徴としてiPhoneを取り上げている。
顕示的消費は昔からあったのだろうが(スミスの時代には、金持ちは上等な爪切りや耳かきを持ち歩いて自慢していたそうだ)、現代はそれが激化し過ぎているために、せっかく社会全体が昔に比べて豊かになっているのに人々の幸福感が減ったりするなどの悪影響をもたらしてしまっている(以前の記事でも紹介したが、顕示的消費の悪影響はロバート・フランクという経済学者が『幸せとお金の経済学』などで論じている)。私自身は、PCやスマホやイヤフォンなどの性能にはこだわらないし服や小道具は安いものしか買わないし車は持っていないしで、幸いにして顕示的消費をするタイプではない(顕示的消費ができるだけの収入を得ていないと言うことだが)。しかし、周りの人間に服やスマホの自慢をされて鬱陶しく感じることはあるし、世間の人々が車の種類とかレストランの立地や値段にこだわっているのを見聞してうんざりしたり呆れたり物悲しくなったりすることは多々ある。
謙虚の美徳が疎んじられて人々が自己顕示に駆られるこの現代社会を見ると、スミス先生も良い気持ちは抱かないだろう。おそらく。
・人は、有徳な人間になることよりも金持ちになったり権力者になることを目指してしまうものだ。人が物資的成功を追い求めてしまうのは、他人から「ひとかどの人物」としてみなされて評価されたい、という欲が人間にはあるからだ。前述したように、幸福になるためには他人からの評価が必要となる。そして、金をいっぱい持っていることそれ自体は幸福に直接つながらないとしても、金持ちであることで人から羨望という評価を得ることは、幸福につながるかもしれないのである。
有名人になることを目指すのも、同様の理由からだ。有名人は、やることなすことが注目されて、よっぽど馬鹿げたことをやらない限りは何をしても好意的な評価をもらえたり羨望のまなざしを受けたりすることができる。われわれは、セレブリティというものに対して異様に弱いのだ。
…世間が重んじるのは金持ちであり、著名人であり、権力者であって、必ずしも賢者や有徳の人ではない。先生もそれに気づいていた。
“だが世間を知るようになると、知恵と徳だけが尊敬されるわけではないし、悪徳と愚考だけが軽蔑されるわけでもないことにすぐに気づく。知恵や徳を備えた人より富と権力を備えた人の方が尊敬の眼で見られる例はめずらしくない。”
(p.115-116)
逆に言えば、身の回りの人から充分な評価を受けている人(または、身の丈にあった評価で満足できる人)は、わざわざ金持ちや有名人を目指したりはしない、ということだろう。つまり、もともと徳のある人や「足るを知る」な心穏やかな人は有名人や金持ちにはならず、そうではない奴が有名人になったり金持ちになったりするということだ。そう考えると、どんどんうんざりしていく。とはいえ…
スミス先生によれば、金持ちになりたいとか、有名になりたいとか、欲張りにも両方になりたいといった野心は、毒である。この毒を飲んではいけない。いったん野心の踏み車に乗ってしまったら、もはや休むことは許されない。
(p.132)
お金自体はけっして悪いものではない。だが、お金のためにお金を追求する愚を犯してはいけない。慎ましく暮らすのがいちばんだ、友よ。
(略)
世の中には、自分よりゆたかな人、自分より才能のある人、自分より有名な人が必ずいる。しかし真にゆたかな人とはどういう人か、とユダヤ教の律法タルムードは問う。それは、自分の運命に満足する人である。スミス先生が言うように、自分の内に名声欲という衝動が潜んでいるということをわきまえたなら、持てるもので満足することが少しは楽にできるようになるかもしれない。
(p.133)
要するに、他人からの評価を得て幸福になるためには「金持ちになったり有名になったりすること」と「知恵と徳のある人間になること」の二つの道があるが、前者の道は茨の道である、ということだ。
・他人から慕われるためには「周囲の人の期待を裏切らない適切なふるまい」をすることが大切であり、適切なふるまいとは、周囲の人の感情や経験を是認して、それに共感することであるそうだ。たとえば、相手がジョークに爆笑したら、それを是認して同調することなどである。
…どうでもいいことだが、私は周囲の人々の感情に同調することがかなり苦手なので、スミスの言う意味での「適切なふるまい」を実践することがほとんどできない。同調するどころか反発してしまう傾向がある。自分がさほど面白くないと思っているコンテンツを周りの人が面白がっていたら、周りの人もそのコンテンツもどんどん嫌いになってしまう、というタイプなのだ。こういうタイプの人は私の他にもいるだろうけれど、みんな人生に苦労していると思う。
・第9章ではイデオロギーの有害性が扱われており、最終章である第10章では例外的に『国富論』に焦点が当てられて現代のグローバル経済の意義が取り上げられているが、それまでの章に比べてこの二つの章はやたらと凡庸で面白くなかった。社会という抽象的でマクロな事柄よりも、スミス自身が様々な人々を観察して考えたミクロな道徳についての文章の方がやっぱり味わいがあって面白いものだ。
モラリストとは、現実の人間を観察することで「人間とは何か」を考えた人たちのことだ。基本的にはフランス語圏の思想家たちを指すことが多いらしいが、古代ギリシャや英語圏にもモラリスト的な議論はフランスに負けず劣らず存在しているものである。