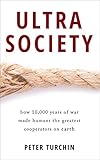theconversation.com
今回紹介するのは、オーストラリアのThe Conversationというサイトに掲載された、哲学者のラッセル・ブラックフォード(Russell Blackford)による「自発的安楽死:信心家にご用心!(Voluntary euthanasia: Beware of godly ! )」という記事。
カンタベリー大主教のジャスティン・ウェルビー(Justin Welby)がイギリスのThe Guardianに掲載した、医師幇助自殺を認める法案を批判する記事に対して反論している記事である。ウェルビーの記事はこちら(
Why I believe assisting people to die would dehumanise our society for ever | Justin Welby | Opinion | The Guardian)
。英語が読める人はウェルビーの記事を先に読んでおいたほうが公平な視点を持てると思う。ブラックフォードは無神論者としても積極的に発言している人物であり、キリスト教的な生命倫理観に否定的であるようだ。
日本における自発的安楽死への反対論には、キリスト教の影響は少ないように思われる。だが、記事内で批判されている「自発的安楽死を認めることは法律や倫理の一線を超える」「自発的安楽死を認めると、本心では安楽死を望んでいない患者も家族や病院や社会からの圧力に負けて安楽死を選んでしまう。社会的立場の弱い人を危険に晒すことになる」「自発的安楽死を認めてしまうと、人間の生命に価値を認めない方向へと社会の倫理や価値観が滑っていってしまう(滑りやすい坂論法)」などの主張は、日本でもよく目にする主張である。その種類の主張に対する反論は意外と目にしないので、今回はブラックフォードの記事を訳して紹介することにした。
「自発的安楽死:信心家にご用心!」by ラッセル・ブラックフォード
イギリスでは、自発的安楽死や医師幇助自殺をめぐって長く続いている社会的・政治的な議論が新しい段階に達した。労働党の議員であるロブ・マリス(Rob Marris)が自発的安楽死に賛成する議員立法を提出し、今月(2015年9月)には庶民院で議論されることになったのだ。イギリスは幇助自殺の問題に関心のある人たちからの注目の的になるだろう。
この記事では、マリスとその支持者によって提案された特定の法案の擁護論を展開する訳ではない。なぜなら、法案に対する批判のほとんどが、自発的安楽死を支持するどんな提案に対しても反対する人たちによるものだからだ。以下では、自発的安楽死に反対する主張について論じよう。その主張は正当化できるだろうか?
「信仰指導者」たちのロビー活動
驚くべきことでもないが、イギリスの様々な宗教団体の指導者たち(「信仰指導者 Faith Leaders」)が、法案に反対するロビー活動を行う連合を結成した。信仰指導者たちの一人である、カンタベリー大主教のジャスティン・ウェルビー(Justin Welby)は、医師幇助自殺への反対を主張する記事をガーディアン誌に掲載した*1。ウェルビーの記事には芝居がかったタイトルが付けられている。「人々が死ぬことを助けることは私たちの社会を永久に非人間的にする、と私が考える理由」。
ウェルビーは以下のように主張している。「私たち[信仰指導者たち]は、"宗教的"な意見を他人に押し付けるためでなく、幇助自殺に関する現行法の変更が人々と社会の両方に有害な影響をもたらすことを懸念して、法案に対する反対意見を書いたのだ」。だが、彼の主張は不誠実だ。
信仰指導者たちが共同して連合を結成したのは、この文脈では「宗教的な意見」といっても差し支えのない意見を主張するロビー活動を議員に対して行うためだ。また、彼らは自分たちの意見が公共政策に反映されること…つまり、他人に押し付けることを求めているのだ。信仰指導者たちは、いつかその日が来た時にも幇助自殺を行うのは止めるように個人を説得しようとしているだけではない。良くも悪くも、ウェルビーと他の宗教的なロビイストたちは、彼らが共有している意見を政府の政策と権力を通じて他人に押し付けようとしているのだ。
とはいえ、他にも重要な問題が残っている。ウェルビーの主張が、非宗教的で説得力のある議論として支持を得られるものであるかどうか、という問題だ。ガーディアン誌に掲載した記事では、ウェルビーは3つの論点を示して主張を展開している。ウェルビーの主張は、いかなる超自然的な概念についても直接には言及していない。だが、(私が推測したところ)ウェルビーの主張は宗教的な前提から完全に切り離されている訳でもない。ロブ・マリスの提案しているような法案を制定することは以下の結果をもたらす、とウェルビーは主張している。
1・法的・倫理的な一線を越えてしまう*2。
2・膨大な数の弱者(vulnerable people)を危険にさらす。
3・もはや「人々の生命について、守る価値・讃える価値・守るために戦う価値を見出す」ことをしなくなってしまう社会をもたらす。
これらの仮定されている結果はいずれも望ましくないものであるから、マリスの提案する法案は受け入れるべきではない、とウェルビーは主張している。さて、彼の主張する仮定のなかに説得力のあるものは一つでも存在しているだろうか?全く存在しない、と私は考えている。
「一線」を超える
幇助自殺を認めることは規範に関する一線を超えてしまうことだ、という主張の詳細は以下のようなものである。「刑法と人権法の核心である、他者の生命に対する敬意が捨て去られてしまうだろう」。だが、この主張は詭弁に過ぎない。幇助自殺を認めるための慎重に規制された手続きの存在は、もはや我々が他者の生命を尊重しなくなることを要求したりほのめかしたりすることには繋がらない。他者の生命について配慮が必要であると見なさなくなる、ということを要求したりほのめかしたりすることもないのだ。
幇助自殺が認められたとしても、計画的に他人の生命を奪うことや無闇に他人の生命を奪うこと(殺人)は、法律によって禁じられたままであるだろう。過失など、殺人程ではないが非難に値する理由によって他人の生命を奪うこと(故殺)も、禁じられたままになるはずである。法律は、他者の生命への敬意に関連している重要な価値に基づいて運営され続けるだろう。むしろ、どのような状況で幇助自殺が認められるかということが法律の文言として入念に記述されることは、個人の生命が法律上でも十分に配慮されることを示すだろう。
生き続けることがその人自身にとって苦しみとなる時点が存在することを、私たちは認めるべきだ。制御できない極度の苦痛に襲われている場合もあるだろうが、身体的な苦痛が制御されているとしても生き続けることが苦しみとなる場合もあるだろう。多くの末期患者は自分自身について様々な感情を抱いているが、とりわけ無力で屈辱的に感じており、かつては人生に喜びを与えたどんな活動も行うことができないと感じている。そのような状況では、自分の人生は実質的にはもう終わっているので、現在はただ引き伸ばさせられているに過ぎない、と感じられる場合もあるだろう。
このように制限されていて不幸な状況では、通常の私たちが死に対して抱く恐怖(殺人に対する恐怖や故殺に対する恐怖、その他の死に対する恐怖など)は、全くもって的外れな感情となる。早まった死を恐れたり死の危害から守られている環境を要求するのではなくて、自分自身の苦しみに満ちた人生を自分で終わらせることができないということに対して、まことに理に適った恐怖を抱くかもしれない。上述した状況において、私が死ぬことを他人が助けてくれることが刑法によって禁止されているとしたら、もはや法律は私たちを恐怖から守ってくれるために存在するものではなくなる。むしろ、恐怖から人々を守ることとは正反対に法律が機能してしまう。私たちが自分の人生を制御するために残された手段が法律によって奪われてしまう。私たちの抱く理に適った恐怖を法律が増してしまうのだ。
刑法の存在する最大の理由は、他人から危害を与えられることから私たちを守るためである。このことに議論の余地はほぼ無い。もちろん、一部の状況では、自分自身の選択の結果から私たちを守るために刑法がパターナリスティックに機能する場合もある。だが、パターナリスティックな法律が存在することに楽観的であるべきではない、と私は考える。一般論として、パターナリスティックな法律は私たちを侮辱して子供扱いするものであるし、私たちの自律を侵害するものである。パターナリスティックな法律に対して私たちは疑い深く審査を行うべきなのだ。
時には、パターナリスティックな規制が特別に必要になる事態も存在するだろう。そのことは私も認めよう。しかし、パターナリスティックな法律は通常ではなく例外的な存在であるべきだ。私たち自身に関する私たちの選択について政府が干渉することは、実際的に可能な限り、できるだけ制限されるべきだ。ある状況においては私たち自身の選択は制限されるべきだと主張するなら、選択を制限するのに見合うその状況に特有の事情というものを示すべきである。特に、私たちの選択に対する干渉が私たちの自律の領域を大幅に減少させるものである場合には。
屈辱的で喜びが無い人生、非常な苦痛に耐え続けなければいけない人生…人生が苦しみに満ちたものとなる時点を過ぎた後にも生き続けることを国家権力に強制させられることは、私たちの自律を根本的に否定することだ。 そのような法律が私たちに敬意を払っているとは言えない。私たち自身の選択に対するこのような「保護」に対して怒りを抱く理由はいくつも存在している。
極限的な状況で死ぬことを選択することが認められたとしても、なんらかの「一線」が超えられる訳ではない。私たちの生命について大いに敬意を示している法律とは、制度や家族からの圧力に対する保護を保証しつつ、資格のある人の援助を用いて自分の人生を終わらせることを選択する余地を残している法律である。
弱者を守る
安楽死を促す不当な圧力から弱者を守る必要性についてはいかがだろうか?この論点については、ウェルビーの主張は他の論点よりも強固である。幇助自殺を認める法律はかなり多くの弱者たちを危険に晒すことになる、とウェルビーは主張している。そのような法律が制定されたならば「この懸念について有効に対処できる予防手段は存在しない。患者の負担を背負わされたくないと思っている、患者に対して非協力的なごく少数の親戚たちから発せられる、かなり陰険な圧力については言うまでもない」。
本当だろうか?本当に、死を選ぶことを選択させる不当な圧力に対して有効に対処できる予防手段は存在しないのだろうか?
たしかに、法律の悪用につながりかねない動機は多く存在しているし、どの動機についても空想上のものだと軽んじることはできない。しかし、イギリスやオーストラリアのような国々に実際に存在している医療文化においては、幇助自殺が最後の手段としてではなく積極的に賞賛されるものとして病院や医師から見なされる程までの変化がそう簡単に起こるということは有り得ないだろう。現時点で存在している医療ケアの文化を失わせるのではなく、医療ケアの文化を反映して補強するように新しい法律を設計することは可能である。
家族内の関係や感情には様々なものが存在しているということをふまえると、家族による法律の悪用の方が、より現実的な懸念であるかもしれない。この懸念は、幇助自殺を合法化することを拒否する理由になるだろうか?
いいや。患者が家族と相談した時に発生するどんな不当な圧力についても、その圧力を軽減するための手続きを法律に導入することが可能であるからだ。家族の意見が与える影響は、他の影響を与えることによってある程度は和らげることができる。専門的なカウンセラーと議論することやアドバイスを受けることを義務化するなどの方法だ。それらの方法の目的は、死を選ぶことを止めるように患者を説得することではなく、死を選ぶという決断が感情的な圧力に対する反応ではないことを保証するためである。
ウェルビーも指摘しているように、死を決断する際の患者が、人生が終わる間際になって自分は他人にとって重荷になっている、と感じているという可能性は確かに存在する。これについては私も認めざるをえないが、このことがショッキングであるとも私には思えない。もし私がひどく無力な状況で、屈辱と苦痛を感じており、私が愛する人たちの資源と時間が私の死を引き延ばすために使われるとしたら、その事実は私の考えに対して影響を与えるだろう。当たり前のことだ。なぜ、その事態に何か邪悪なことが含まれているかのように想像したり装ったりする必要があるのだろう?
私の人生が引き延ばされることによって他人に対してもたらされる影響について私が思考してしまうことは、ほとんど避けられないことである。死を選ぶかどうかという決断にとって、それは充分に関連性がある事柄であるのだ。また、他人に対する影響が私の思考の対象となったとしても、私が自分自身の人生を生き続けることが喜びが無く、苦痛で、もどかしく、屈辱的であると思っているとしたら、他人に対する影響がそれらの感情に取って代わる訳ではない。私は他人に対する影響と自分自身の人生について同時に考えるだろうし、後者の方が私にとっては重要に思えるだろう。たしかに、医療的な援助によって死のうと決断した人たちの多数が、自分が他人に対して重荷になっているということを決断の理由の"1つ"として挙げている。だが、ウェルビーが行っているようにその"1つ"の理由に注目して大体的に取り上げるのはアンフェアである。他人にとって重荷になっているという感情が影響していることは、予想できることなのだ。
より正当な懸念として、患者を適切に保護するための手続きはあまりに要求が多くて複雑なものになるから実際には有効に機能しないだろう、という予測がある。その手続きは患者による死の決断を妨げるだろうし、実際には苦しみを増して意図していない侵害を起こすかもしれない。意図しているものとは反対の結果が生じることになる訳だ。
ウェルビーが実際に主張している議論以上に、上述の議論には説得力がある。とはいえ、この議論は必要以上に悲観的である。法律の悪用の可能性を最小化するための手続きが実用的に機能するように設計することは可能であるはずだ。
詳細な手続きの範囲内にきちんと含まれないような事例についても、「慈悲殺」の例に倣って比較的広い範囲の擁護論を主張することは可能であるだろう。いずれにしても、現在のイングランドとウェールズには医師が自殺幇助を遂行する際の処置に関するガイドラインが存在している*3。死を選ぶことについての安定していて、明確で、充分な情報に基づいた決断を「犠牲者」が下している際や、自殺に対する幇助が同情にのみ基づいている場合であったとしても、処置が行われる可能性はガイドラインによって低くされている。
公平のために記しておくが、ウェルビーもこのようなガイドラインを否定してはいない。安楽死に関する法律改正が制定されたとしても、残酷な処置から患者を守るための保護を追加するためのガイドラインを維持することが妨げられる訳ではないのだ。
「滑りやすい坂」を滑る?
ウェルビーの第三の論点は明らかな長所もないものだ。その論点は、滑りやすい坂論法と似通ったものである。私たちが自殺を合法化してしまったなら、私たちの社会はもはや「自殺を考えるほどの年齢や段階に達してしまった人に対して、愛情やケアや同情を示すことが無くなってしまう」し「人々の生命について、守る価値・讃える価値・守るために戦う価値を見出す」ことを行わなくなるであろう、とウェルビーは示唆している。
第三の論点は第一の論点に少しだけ議論を付け加えたものに過ぎないし、第一の論点と似たり寄ったりの問題を抱えている。幇助自殺を合法化しつつつ規制する法制度が存在することは、自殺を考えている人への「愛情やケアや同情」に欠ける社会であることとはいかなる意味でも繋がらない。絶望的としか言いようがない状況に陥ってしまった人や生き続けることが自分にとって苦しみであると感じられる人に対して、彼らが自分の人生を終わらせることを認めるということは、そのような人々に対して本人の意思に反してでも生き延びることを要求する社会と比べて、社会がより多くの同情を示しているということなのだ。
しかし、第三の論点には他の主張も含まれている。その生命を持つ本人自身が生き続けることについて価値を見出せる段階を過ぎたとしても、我々は人々の生命を「守るために戦う価値」があると見なさなければならない、という主張だ。
もう死んでしまいたいと人に思わせるような、一時的ではあるが非常に衝撃的な事態が多数存在することには疑いがない。そのような事態が起こった時には、その事態で苦しんでいる人を助けて気を安らげるために、私たちはできる限りのことをするだろう。そして、早まったことをしないように思いとどまらせようとするはずだ。しかし、だからといって、苦痛であり惨めであると本人が感じている経験に耐え続けている末期患者の人に対しても、その人を生き続けさせるために我々は力の限りを尽くすべきだということにはならない。
同情のある人なら、耐え難い生を送っている人を本人の意思に反してでも生き続けさせるべきだ…そんな主張を正当化する理由で、宗教的でないものは聞いたことがない。その人の生を終わらせることの援助を否定し続けるとは、傲慢で残酷に思えてもいいはずである。
神や運命などの超自然的な仮説を受け入れたならば、人の生を終わらせることの援助を否定し続けることも正当化できる。いつ人が死ぬかということは神や運命が決めているのであり、幇助自殺を含めた全ての種類の殺人は神の特権を侵害することだ、という訳である。イギリスの信仰指導者たちによる意見の裏にもこのような考えが潜んでいるはずだ、と私には思える。だが、このような宗教的な考えは、世俗的な法律に携わる政治家や官僚に影響しようとするべきではないのだ。
信心家にご用心
生命の始まりと終わりに関する問題について、ウェルビー大主教のような宗教的指導者たちが知的権威や道徳的権威などの特定の権威を持っている訳ではない。宗教的指導者たちはそれぞれが所属している宗教の教義の専門家ではあるが、その宗教と関係ない人々にとっては意味の無い専門性であるのだ。
もちろん、宗教的指導者たちも、公共空間における議論に参加する権利を持っている。自由民主社会に暮らす他の全ての人々と同じように、宗教指導者にも言論の自由は存在しているのだ。だが、宗教指導者が主張している議論だからといって、その議論に信憑性が付け足される訳でもない。超常的な存在がいるという仮定に依存している限り、彼らの議論は政府による政策の基盤としては不十分である。宗教的指導者たちが自分たちの主張を非宗教的で現世的な言葉に言い換えたらなら、私たちは彼らの主張に利点があるかどうかについて検討することができる。だとしても、多くの場合は彼らの主張には説得力が無いと判断することになるだろう。
以前に私のブログに掲載した短い記事で言及したように*4、ウェルビーのような宗教家たちによる「心からの同情 profound compassion」というレトリックには、退屈で、鬱陶しく、そして独り善がりなところが含まれている。実際には同情的でない人や実質的には苦痛を減らすことになる政策を支持しない人であっても、「同情」や「同情のある」という言葉を持ち出すことはできる、という点に注意しよう。「心からの」という単語についても同じである。このような単語で飾り立てることで、自分の議論を聖人っぽく厳粛に見せることができる訳だ。昔ながらの効果的なレトリック戦略である。
素直な無神論者であるオフェリア・ベンソンは、私以上にウェルビーを批判したブログ記事を書いている*5。ベンソンは、ウェルビーのレトリックの大半を感情的な脅迫だとみなしている。私とベンソンとは別の問題については相容れないこともあるが、今回については彼女の意見が正しいと私も思う。ガーディアン誌に掲載されたウェルビー大主教の記事の大部分は、巧妙で操作的な言葉によって書かれている。読者に恥の念を与えることと、自分の議論に感心させて同意させることを意図している言葉だ。ベンソンはウェルビーの議論にどぎつい言葉を与えている。「たわごと」、「でたらめ」、「ブルシット」。
私はウェルビーの議論をプロパガンダと呼ぼう。