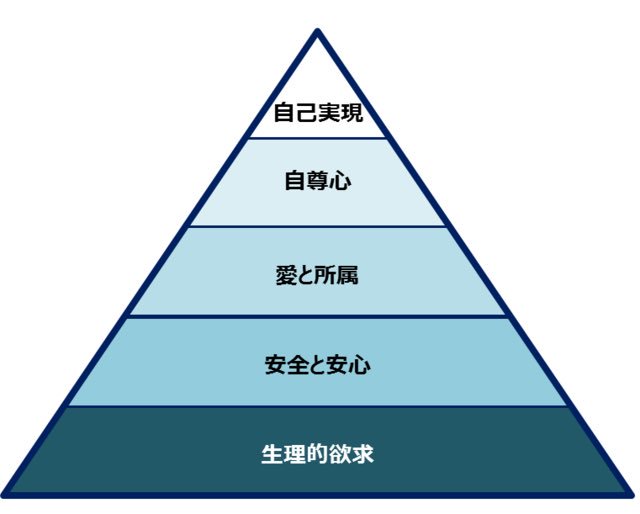前回の記事でも紹介した、心理学者のロウ・バウマイスターの著作『Is There Anything Good About Men? :How Cultures Flourish by Exploiting Men(男にいいところはあるのか?:文化はいかに男性を搾取して繁栄するか)』を読み終えたので、軽く内容をまとめてみよう。
この本では、進化心理学と文化進化論の考え方を用いながら、社会における男性と女性それぞれの役割や扱われ方などが分析されている。バウマイスターは「エッセイ」であると表現しているが、学術的な文献からの引用も多く、セミアカデミックな内容だといえるだろう。
この本の前半では、まず、男性と女性に関するいくつかの生物学的な事実が提示される。
・男性と女性とで、どちらかの方が能力が優れている、ということはない。
・男性と女性との間に能力の優劣はないが、関心や傾向には男女差が存在する。
・男性の間の能力や性質の差のばらつきは、女性のそれよりも大きい。多くの能力や性質について、両極にいるのは、どちらも男性である。
・繁殖の成功については、女性は安定しているが、男性は不安定である。女性の場合は、生涯で産める子供の数に限りはあるが、多くの女性は子供を残すことができてきた。男性の場合は、性に関する競争の勝者たちが大量の子供を残してきた一方で、まったく子供を残さないまま死んでいった敗者たちの数はそれ以上に多い。
・繁殖戦略の違いから、男性はライバルである他の男性たちに対して優位に立とうとする。そのため、男性はリスク追求的であり、競争的で、野心的で、積極的である。
・「社会性がある」ということには二つの意味がある。親密な関係を築けている相手が複数いるということか、親密ではないが数多くの相手と関わったり名を知られたりしているか。女性は社交的な存在であるとよく言われるが、多くの女性は、前者の意味での社会性を志向しても、後者の意味での社会性は志向していない。一方で、多くの男性は後者の意味での社会性を志向している。
これらの生物学的な事実を前提としたうえで持ち出されるのが、「文化進化論」的な考え方だ。
ここでいう「文化」とは、衣食住や言葉や芸術などのいかにも文化っぽいものに限らず、政治や経済や法律などに関する諸々の社会制度を含めた、広い意味での「文化」である。
人間の社会は、文化を生み出すことで、生産力を高めて飢えや欠乏を防いだり、安定性を高めて人々が共同作業を行いさせやすくした。根本的には、文化とは、人間の生存と繁殖を有利にするために存在している。
そして、文化は、異なる文化と競合する。異なる集団が二つあるとき、どちらかが生き残るかは、「どちらの人口の方が多いか」ということや、どちら武器の方が発達しているか、どちらの戦士たちの方がより秩序立っていて命令に従うか、ということによって決まる。そして、効率的に機能する文化ほど、その集団の人口を増やして、優れた武器を生み出して、構成員を従わせる秩序を成立させることができる。逆に言えば、非効率的な文化は、それよりも効率的な文化によって淘汰されてしまうのだ。
具体的には、「情報の蓄積と伝達」「分業、専門化」「交換、交易」といったことをより効率的に実現できる文化の方が、生産力を上げて集団の人口を増やしやすい。
また、文化が効率的であるいうことは、たとえば「集団の人口を増やす」という目的を達成するために、その集団の構成員をより効率的に利用・搾取する方法を編み出している、ということである。文化は集団を存続させることに貢献するものであるが、個々の構成員を幸福にするとは限らない。
そして、他の文化との競争に勝って現在まで生き残ってきたような文化は、生産や秩序や発明を効率的に達成するために、男性を搾取してきた。
なぜ、女性ではなく、男性の方が文化によって搾取されてきたのか?
主たる点は、男性は女性よりもリスク追求的であり競争的な性質を持つ、ということにある。たとえば、効率的な文化には発明や投資が欠かせないが、発明や投資は当たれば得るものが大きい代わりに外れたら得られるものが何もない、リスクの大きい行為である。また、公立的な文化は宗教的権威や政治体制などによる権力を通じて秩序をもたらすものであるが、権力者になろうとするためには他の相手との競争に勝たなければならない。勝者になる可能性もあれば、敗者になる可能性もある。
平均的に見れば、女性たちは複数の相手と親密な関係を築ければ満足できて、発明や権力といった競争的な世界には興味を示さない。一方で、リスク追求的であり不特定多数のなかで抜きん出た存在になることを望む男性たちは、競争的な世界に惹き付けられる。そのために、「男は仕事、女は家庭」式の性別分業が発達するようになった。
また、男性は女性よりも特徴にばらつきがあり極端であるということは、多様なアプローチを生み出させて、発明やイノベーションを効果的に機能させやすくする。
こうして、文化が効率的であるために欠かせない富・知識・権力は、競争的な男たちの世界で築かれていったのである。これが、女性たちを富・知識・権力にアクセスさせない、ジェンダー不平等の起源でもある。
文化は、競争に勝ち抜いた男たちには、報酬を与えてきた。
しかし、勝ち抜くまで至らない大半の男性たちは、使い捨ての消耗品のように扱われる。
そもそも、「集団の人口を増やす」という観点からすれば、女性は一人につき生涯で出産できる数に限りがあるために、女性の数は多ければ多いほどよい。一方で、一人あたりの男性の精子はほとんど尽きることがないから、多数の男性が必要ということはない。つまり、男性の生命は、女性の生命に比べて価値がないのだ。
そのために、他集団との戦闘や、生死に関わる危険な仕事に駆り出されるのは、大半が男性である。文化からすれば、個々の男性の生命を守る理由は乏しいのだ。
ただし、いくら男性がリスク追求で競争的であるとしても、なんのメリットも見えないことに対して自分の人生を犠牲にするということはできない。そのため、効率的な文化であればあるほど、集団の発展と防衛のために欠かせない、危険な領域や当たり外れの大きい領域に男性たちを飛び込ませるための「誘因」を発展させてきた。
競争に勝ち抜いた者に多大な報酬を与えることも、誘因のひとつだ。その報酬は、物質的なものであるとは限らず、評価や名誉に関するものでもあり得る。家事や再生産労働などの「女の世界」に属するものよりも、富・知識・権力などの「男の世界」に属するものの方が社会的に尊重されて高評価されてきたのは、そうした方がより多くの男性たちを「男の世界」に飛び込ませることができるからだ。
さらに、文化は「男らしさ(Manhood)」に関する社会規範を構築してきた。たとえば、「男たるもの、自分が消費するよりも多くのものを生産しなければならない」という規範などである。女性は子供を産むことさえできればそれで「生産的」な存在となり得るが、男性はそうではないので、規範によるプレッシャーを与えて生産的な領域へと追い立てなければいけない。
つまり、「男らしさ」とは男性が生まれつき身につけているものではなく、獲得しなければならないものである、と設定されたのだ。男性は、なにかをしなければ、一人前の男であるとは見なされない。これにより、競争やリスク追求に対する志向に乏しい男性たちであっても、それらの世界に飛び込まざるを得なくなる。
また、すべての男性が平等に尊敬されるのではなく、勝者のみが尊敬されて敗者は軽蔑されるような規範を成立させることで、「負け犬」とみなされることを恐れる男性たちの競争に対するプレッシャーを増させられる。これにより、男性同士の競争を激しくさせて、経済や投資や発明などをより効率的に機能させることができるのだ。
そして、結婚制度は、男性が「男の世界」で獲得してきた富を、女性の性的資本と交換するためのシステムであるといえる。女性は、男性の性的な欲求を利用して、結婚を通じて男性から物質的な財産を搾取している、と捉えられる。
バウマイスターの問題意識の主たる点は、フェミニズム理論による、「家父長制」などの用語を用いた社会分析に対する不満にある。
フェミニストたちは、男性社会を一枚岩であると捉えて、「男同士は結託して共謀しており、女性たちを富や権力や知識から排除して、抑圧して差別している」と考えがちだ。最近では「男性特権」という言葉も使われるようになってきたが、この言葉も「男性は男性であるというだけで、女性に対して構造的に優位に立っている」ということを指し示している*1。そして、男性は自分たちの特権を放棄して、現時点で構造的に劣位にいる女性たちを引き上げるために彼女たちを手助けしたり自分たちの利益を後回しにしたりすべきだ、ということが論じられるのだ。
しかし、この本のなかでバウマイスターが繰り返し強調しているように、「男性たちは共通の利益を確保するために共謀しあっている」ということも「男性は男性であるというだけで、男性特権の恩恵にあずかれる」ということも、事実からは程遠い。
この本のなかでよく引用されるのが、レズビアン女性でありながら一年弱のあいだ男性に扮して「男として生きるとはどういうことであるか」を体験した作家、ノラ・ヴィンセントによる Self-Made Man という著作だ*2。フェミニズムの考え方に影響されて「男として生きるということは、特権にあずかれてラクなことであるに違いない」と考えていたノラは、実際には「男性としての人生」は熾烈な競争にさらされており、誰かが世話したり構ってくれたりすることもなく、自分の存在価値を自分自身で証明しなければならないものであることを発見して衝撃を受けたのだ。
集団内では、個人としての男性は他の男性と競争しあっている。他の男性との競争に勝てば富や権力や名誉などの報酬が得られて繁殖にも成功するが、負けてしまうと、手元にはほとんど何も残らず繁殖をすることもできない。前回の記事でも書いたように、フェミニストたちの考え方の問題点のひとつは、社会で成功を収めたこと富や権力を握っている「上」の立場にいる男性ばかりを見てしまい、「下」の立場にいる男性は目を向けない、というバイアスがかかっていることだ。そのため、男性内に競争が存在するという事実、そして競争に負けて惨めな状態で生きる男性たちが数多く存在しているという事実を考慮することができなくなっているのである。
また、集団同士の争いを見ても、ある集団内における「男性たち」がグループとして争いの対象とするのは、同じ集団内の「女性たち」というグループではなく、別の集団の「男性たち」というグループだ。だからこそ、男性たちは、女性たちを含む自分の集団を守るために自らの生命を危険に晒すのである。
社会において男性たちが優位であるように見えるとしたら、その理由の一部は、富や知識や権力の大半は実際に男性たちによって創造されてきたこと、女性たちは(能力ではなく関心や傾向のために)それらの創造に貢献してこなかったことに由来している。また、「男の世界」に属する物事に高い評価を与えて報酬を吊り上げなければ、そこに男性たちを飛び込ませることができず、他の文化に比べて非効率的な文化となって淘汰されてしまう、ということもある。
いずれにせよ、ジェンダー不平等は、男性たちに対する女性への陰謀ではなく、男性と女性の両方を効率的に利用する文化進化のメカニズムによって作られてきたのである。
バウマイスターも、富・知識・財産に関心のある女性たちがその世界から弾かれてきたという事実が存在してきたことは認めている。ただし、それは現時点で効率的に動くシステムに変更をもたらすことを拒む現状維持バイアスによって説明できる、ともしている。女性に対する「抑圧」が歴史上に存在してきたことは否定できないとしても、それはあくまで二次的なものである、と論じているのだ。
一方で、「女性の目」に基づいて世界を分析するフェミニズムは、主観性のバイアスにより抑圧の存在を実際以上に過大評価してしまう。
1970年代頃から、フェミニズムによって「社会における様々な分野に女性の数が少ないのは、構造的な女性差別が原因だ」という考え方が浸透したことにより、欧米の先進国では多くの領域で女性に対する優遇措置が取られるようになった。教育の場でも、男の子は後回しにされて、女の子を応援して自信を身に付けさせることが優先されるようになった。
しかし、たとえば政治や自然科学を志す女性たちの数が少ない原因は女性差別ではなく彼女たち自身の志向や傾向に存在するとしたら、いくら優遇措置を取ったところでその効果には限界がある。
さらに、女性に対して優遇措置をとるということは、男性たちからすればその領域にコミットしても得られるメリットが少なくなるということだ。そのために、本来ならその領域で活躍していたかもしれない男性たちが立ち去ってしまい、結果として、その領域の効率性や生産性が下がってしまうかもしれない。文化進化論の観点からすれば、そのような優遇措置をとる集団は、やがて他の集団に負けてしまう可能性が高いのである。
ジェンダーに関する議論は、フェミニズムのものにせよ「男性学」や「弱者男性論」のものにせよ、自身が性役割に苦しんでいたり性規範を不愉快に思っている人たちによって主導されることが多い。そのため、性規範や性役割のミクロなデメリットが強調されてそれらを解体する必要性が論じられることが多く、性規範や性役割が社会にもたらすマクロなメリットについては無視されてしまいがちだ。
一方で、バウマイスターの議論では、消耗品として文化から使い捨てられる「負け犬」男性たちに対する同情は強く感じられるものの、男性が「男らしさ」への渇望を捨てて社会から競争が失われたり、いざという時に自分を犠牲にして身近な人や社会を守ろうとする人がいなくなることについての懸念も強く示されている。性役割やジェンダー不平等の「罪」だけでなく「功」についても紙幅を割いているところが、文化進化論の枠組みを採用したこの本ならではのオリジナリティだと言えるだろう。
とはいえ、バウマイスターの議論にもいろいろと懸念点はある。
前回に紹介したように、この本の冒頭では「男性と女性は対立している、という見方は採用しない」という主張が打ち出されるが、最後まで読んでみると、かなり「男性寄り」で自己憐憫的な議論がされている感は否めない。
たとえば、「男性は女性と対立していない」ということの根拠として持ち出されるのが、女性参政権運動では男性の多数派も女性に参政権を与えることに賛成したということであったり、男性によって発明・発展させられてきた医療によって女性たちも救われてきたということであったりする。これらの議論は、率直に言って、恩着せがましくて面の皮が厚いものであるように思われる。
また、政治や経済や発明などの領域から女性が弾かれてきた理由を「現状維持バイアス」や「二次的なもの」として説明している点にも、不安がのこるところだ。
たとえば2018年に発覚した日本の大学の医学部不正入試問題などは、女性への排除が現代でも意識的に行われていることを明らかに示す事例であるように思われる。アファーマティブ・アクションなどによって女性を優遇しすぎることが非効率的であるとしても、女性の排除を継続することで能力がある女性たちを活用する機会を失いつづけることは、さらに非効率的であるだろう。実際、現代の先進国を比較しても、女性が政治やビジネスの領域で支障なく活躍できている国は、そうでない国に比べて生産性や効率性が高くなっているように思われる。それにも関わらず女性の排除を継続している国や領域が存在しているという点は、効率の観点だけからは説明できないはずだ。
結局のところ、フェミニズムが指摘するような「女性に対する抑圧」や「ミソジニー」などの問題が多かれ少なかれ存在することは否定できないのである。その影響力や規模は、バウマイスターが想定しているよりもずっと大きいものであるはずだ。